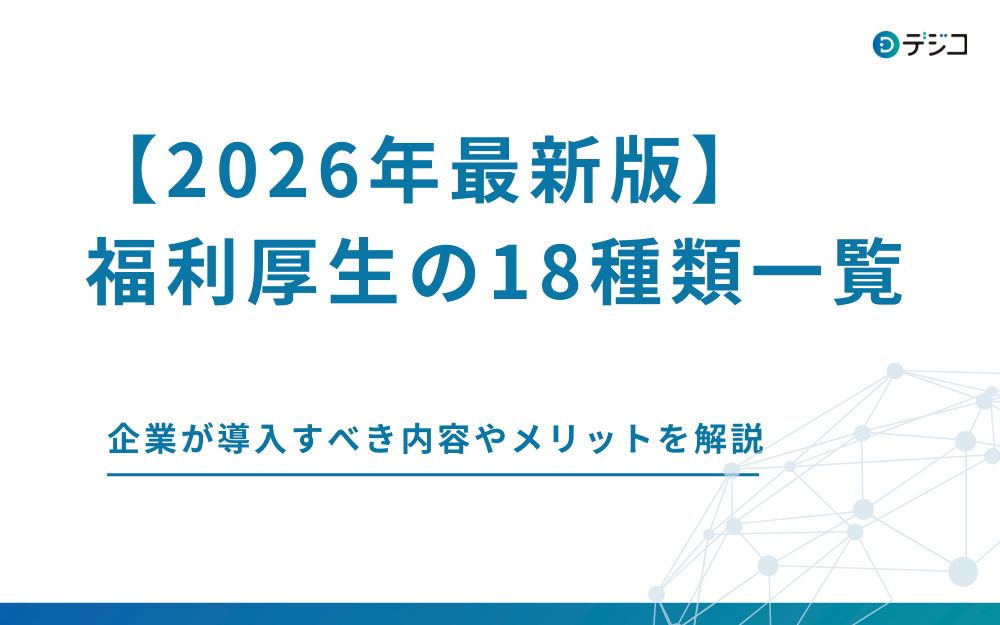
【2026年最新版】福利厚生の18種類一覧!会社が導入すべき内容やメリットを解説
福利厚生には、健康保険のように法律で決められた制度もあれば、社員食堂など企業が独自で取り入れる内容もあります。
福利厚生が充実していないと、従業員の離職や仕事に対するモチベーション低下につながります。
従業員のモチベーション低下は、企業の長期的な成長に悪影響を与える可能性もあるため、福利厚生を充実させることは重要です。
そこでこの記事では、計18種類の福利厚生を一覧で紹介し、その内容や特徴をまとめました。
「福利厚生にどのような種類があるか知りたい」「福利厚生を充実させたい」と考えている場合は、ぜひ最後までご覧ください。
デジコでは、福利厚生として従業員に贈れるデジタルギフトサービスを提供しています。
Amazonギフトカードなど、人気の高いギフトを含む最大6,000種類のなかから従業員が好きなアイテムを選べるので、従業員満足度の向上にもつながります。
デジコの詳細を知りたい方は、以下から気軽にサービス資料をダウンロードください。
デジコの資料をダウンロードする
目次 []
福利厚生とは

福利厚生とは、給与や賞与以外で社員に提供する報酬・サービスのことです。
福利厚生が充実しているかどうかは、社員が仕事をしながら生活するうえでの満足度に大きく影響します。
例えば、住宅手当があることで社員の家賃負担が軽減され、休暇制度が整っていれば、ワークライフバランスを保てます。
福利厚生の充実により、社員が心地よく働ける環境が整うからです。
従業員が恩恵を受けられるため、福利厚生の整備は企業全体の満足度向上に貢献します。
また、「福利厚生が充実している企業=社員思いの企業」という印象を与えることで、自社で働きたいと考える人が増えるきっかけにもなります。
福利厚生の基本について詳しく知りたい場合は、以下の記事で解説していますので、ご覧ください。
福利厚生は2種類に分類できる

福利厚生は、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の大きく2種類に分類できます。
| 法定福利厚生 | 法定外福利厚生 |
|---|---|
|
|
法定福利厚生とは、法律で企業に義務付けられている福利厚生です。
病気やケガによる金銭的負担を軽減する医療保険や、失業時の生活をサポートする給付金制度などがあります。
法定外福利厚生は、企業が独自に導入できる福利厚生です。
どの福利厚生を採用するかは企業ごとに任せられており、企業の独自性や他社との差別化を図りやすくなっています。
法定福利厚生と法定外福利厚生の種類について、さらに詳しく見ていきましょう。
【法定福利厚生】全6種類と内容一覧

法定福利厚生の6種類
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 子ども・子育て拠出金
法定福利厚生には上記の6種類があります。それぞれどのような内容なのか見ていきましょう。
1.健康保険
健康保険は、社員の病気やケガによる金銭的負担をサポートする医療保険です。
病院で健康保険証を見せると、治療代や診察代の自己負担が3割となり、残りは保険でカバーされます。
協会けんぽや各健康保険組合が運営し、所定の条件を満たした社員とその社員の扶養家族が、健康保険の加入対象です。
さらに高額療養費制度により、医療費が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。
支払額の上限は収入額に応じて設定されているため、大きなケガや病気が発生しても、経済的な過度な負担を避けられる仕組みです。
また、医療費の負担を軽減するだけでなく、健康診断や病気・ケガによる休職をサポートする給付金制度(傷病手当金)など、社員の健康管理と生活保障を支える制度が整っています。
最近では、オンライン診療も保険適用となっており、社員は自宅で医療サービスを受けられるため、通院の手間を省きながら治療が可能です。
2.厚生年金保険
厚生年金保険は、国民年金保険に上乗せして支払う年金保険です。
厚生年金保険に加入し納付期間などの条件を満たすと、老齢年金・遺族年金・障がい年金が基礎年金に上乗せして受け取れます。
なお、厚生年金保険料は会社と社員が折半で支払います。厚生年金保険の適用事業所で働く70歳未満の人は、原則として全員加入が必要です。
また2022年の法改正により、70歳以上でも企業と従業員の合意があれば加入可能になりました。
60歳以降も働きながら年金を受給する在職老齢年金制度もあり、一定の収入を超えた場合には年金額が調整されます。
参考:日本年金機構
3.介護保険
介護保険は、介護が必要な人を相互扶助で支える保険制度です。
40歳以上の人が加入対象(被保険者)となり、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。
被保険者は、介護サービスの支援やバリアフリー改修費用の補助などを受けられます。
ただし、介護保険サービスの対象は、日常生活を送るうえで必要な支援や自立を助けるための最低限のサービスに限られ、それ以上のサービスは保険適用外です。
40~64歳の人(第2号被保険者)は、末期がんや関節リウマチなどの特定疾病に該当する場合のみ、介護保険のサービスを受けられます。
また介護保険の給付とあわせて介護休業制度を活用することで、仕事と介護の両立が可能となります。
4.雇用保険
雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を図るための保険制度です。
失業手当や育児休業給付金などがあり、雇用や収入が不安定になりやすいタイミングで金銭的サポートを受けられます。
雇用保険の加入対象は正社員に限らず、所定の労働時間や雇用期間などの条件を満たしたパート・アルバイトも含まれます。
また、副業・兼業の場合でも、各雇用先で条件を満たせば雇用保険の適用対象です。
5.労災保険
労災保険は、業務中に病気やケガをした場合に保障を受けられる保険です。
雇用保険と労災保険はあわせて「労働保険」と呼ばれます。
健康保険でも病気・ケガに対するサポートはありますが、労災保険は勤務時間中や通勤途中の病気・ケガに限定される点が異なります。
在宅ワーク中の事故も、業務との関連性が認められれば労災保険の対象です。
労災保険料は企業の全額負担となり、社員の負担はありません。
6.子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)は、子育てや育児を支援する目的で設けられた制度です。
集まったお金は、児童手当の支給や地域の子育て支援事業などに使われており、2019年から始まった幼児教育・保育の無償化にも活用されています。
子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険の加入事業所が全額負担するため、子どもがいる社員は企業から間接的に子育て費用の支援を受けているといえます。
また、育児休業給付金などの育児支援制度を併用することで、子育て中の家庭の負担を大きく軽減でき、仕事と育児の両立をサポートする仕組みです。
【法定外福利厚生】全12種類と内容一覧

法定外福利厚生の12種類
- 財産形成
- 食事補助
- 健康・医療
- 休暇
- 余暇・レクリエーション
- 自己啓発
- 慶弔・災害
- 住宅補助
- 働き方
- 育児・介護の両立支援
- 通勤支援
- 高齢者支援
企業が独自に導入できる法定外福利厚生は、大きく分けると12種類あります。
それぞれどのような内容なのか、具体的な手当や制度の例も交えて見ていきましょう。
1.財産形成
例
- 財形貯蓄制度
- 社内預金制度
- 社内貸付制度(従業員貸付制度)
- 持株会、ストックオプション制度
- 金融関係の相談、セミナー制度
社員の貯蓄を助ける仕組みや、マネーリテラシーを向上させるための制度などが財産形成の福利厚生です。
給与を上げるといった直接的な還元を社員にしたくても、企業の業績なども関係するため、そう簡単ではありません。
そのため、以下のような形で社員の財産形成をサポートできます。
- 社内預金制度で高金利の預け入れ先を提供する
- 金融セミナーを開催し、資産運用に必要な知識を提供する
- 確定拠出年金(企業型DC)やNISA・iDeCoの導入をサポートする
- NISAなどの非課税投資制度を活用した資産運用セミナーを開催する
これらの取り組みが社員の経済的な安心感を高め、長期的なキャリア形成を支援します。
2.食事補助
例
- 社員食堂
- お弁当や仕出し弁当の提供
- 提携の飲食店の食事補助
- 食事券や食事カードなどの配布
健康経営(社員の健康管理も企業課題としてとらえる考え方)の観点から、食事補助は企業が重視する福利厚生の一つです。
社員の健康状態は、仕事のパフォーマンスに大きく影響します。
そのため、社員食堂で栄養豊富な食事を提供するなど社員の健康に配慮することも、福利厚生の一環です。
食事券や食事カードの配布も、喜ばれる福利厚生の一つです。社員が好きなメニューやおいしいランチを食べることで、モチベーション向上にもつながります。
3.健康・医療
例
- 定期健康診断の実施
- メンタルヘルスケア
- 人間ドックの受診補助
- 医療費補助
- ジムの利用補助
- 健康相談窓口の設置
- 健康管理アプリの導入
健康や医療に関する福利厚生は、健康経営の観点から企業が重視するサポートの一つです。
身体的にも精神的にもサポートがあることで、社員は安心して働くことができる環境が整います。
具体的には、定期検診の実施や人間ドックの受診補助に加え、ジムの利用補助なども社員から喜ばれる福利厚生です。
また、オンラインでの健康相談サービスや、リモートワーク中でも利用できるメンタルヘルスケアプログラムの導入が増加しており、働き方の多様化に対応した福利厚生として注目されています。
4.休暇
例
- リフレッシュ休暇
- ボランティア休暇(被災地などのボランティアへ行くための休暇)
- アニバーサリー休暇(誕生日や結婚記念日などの休暇)
- 夏季・冬季休暇(夏休み、冬休みで有休以外に+数日の休暇)
- 特別有給休暇制度(結婚、出産、勤続祝いなどの特別な休暇)
法律で定められた有給休暇以外に、会社が正式に認める休暇制度も福利厚生の一つです。
休暇制度が整っていると社員は気兼ねなく休める機会が増えるため、ワークライフバランスの向上につながります。
5.余暇・レクリエーション
例
- 社員旅行
- 社内部活・サークル活動
- 交流会・親睦会
業務内容には直接関係しない社内の行事やイベントは、余暇・レクリエーションの福利厚生です。
余暇・レクリエーションの福利厚生があると、社内のコミュニケーションの活性化や、社員の気晴らしになる効果を期待できます。
6.自己啓発
例
- 資格取得支援
- 自己啓発セミナーの参加費補助
- 本の購入費補助
- 留学・海外研修の補助
社員の自己啓発のための費用を、企業が補助する福利厚生もあります。
自己啓発のジャンルは幅広いため、業務内容に関係する「資格取得」や「セミナー参加」を補助対象にするのもおすすめです。
自己啓発により社員が心身ともに成長し、身につけた知識やスキルを仕事に活かしてもらうことを望めます。
7.慶弔・災害
例
- 慶弔見舞金制度(結婚、出産、死亡弔慰など)
- 傷病・災害見舞金(傷病で休業、災害で被害を受けたとき)
- 開店・開業祝い(独立開業した社員などへのお祝い)
- 永年勤続表彰
慶事や弔事の際に、企業の心遣いを示すのも大切な福利厚生です。
結婚式などの冠婚葬祭の行事に限らず、企業としてお祝いしたいことや支援したいことを、福利厚生の対象に含めることで、企業の独自性や他企業との差別化を図れます。
8.住宅補助
例
- 家賃・住宅手当
- 社員寮・社宅
- 住宅ローン補助
- 寒冷地手当(雪国の暖房代補助)
社員の住まいに関する資金サポートをおこなうのが、住宅補助の福利厚生です。
毎月30,000円など一定額の家賃手当を出したり、格安の家賃で社宅を貸し出したりします。
また、雪が降る寒い地域では暖房代が高額になるため、寒冷地手当として一時金を支給する企業もあります。
9.働き方
例
- フレックスタイム制度
- 時差出勤制度
- 短時間勤務
- プレミアムフライデー
- ノー残業デー
勤務時間や働き方に関する福利厚生があると、多様な働き方の推進が可能です。
「家庭の事情で短時間勤務をしたい」「通勤ラッシュを避けるために時差出勤をしたい」のような社員のニーズを満たせます。
10.育児・介護の両立支援
例
- 育児休業の延長制度
- 社内保育園・託児所の設置
- ベビーシッター補助金
- 介護費用補助
社員が育児や介護をしやすいよう、働く環境を整えるのも福利厚生として重要です。
労働政策研究・研修機構の調査によると、共働き世帯は年々増加しています。
そのため、家庭と仕事を両立できる環境を整えることが求められているのです。

また、高齢化社会の影響もあり、介護関連の福利厚生は今後ニーズの高まりが予想されています。
こうした背景から、介護離職防止のための在宅勤務制度の拡充が進んでいます。
他にも、注目されているのは男性の育児休業取得率を高めるための施策です。
11.交通関連
例
- 通勤手当
- 駐車場の補助
社員の自宅から企業までの移動にかかった費用を、福利厚生として一部または全額負担できます。
公共交通機関を利用する社員に限らず、自転車やマイカー通勤の場合でも距離に応じて手当をもらえることが多いです。
12高齢者支援
例
- ライフプランセミナーの開催
- 再雇用制度や継続雇用制度の導入
- 高齢者向けの健康診断の実施
- 企業年金制度の充実
- 退職金制度の整備
- 高齢者の経験やスキルを活かすための知識継承プログラムの実施
退職後の生活に対する不安を軽減することも、重要です。
例えば将来のライフプランに関する知識や経済的な準備を支援することで、老後の生活設計が容易になります。
また再雇用や継続雇用制度の導入により、高齢者がその経験や知識を活かし働き続けることで、企業の生産性向上にもつながります。
ここまで、18種類の福利厚生を紹介してきました。
「18種類もあるなかで、どのような福利厚生が喜ばれるのだろう?」と迷ったときには、福利厚生としてデジタルギフトを提供しているデジコにご相談ください。
デジタルギフトは、多くの企業から満足度が高いギフトとして選ばれています。
詳しいデジタルギフトサービスに関する調査結果が知りたい方は、こちらからダウンロードできます。
福利厚生費の予算目安と最低ライン

福利厚生費は、従業員の生活をサポートし、働きやすい環境を整えるための重要な費用です。
日本経済団体連合会が、2019年度に実施した「第64回 福利厚生費調査結果報告」によると、従業員1人当たりの1ヵ月の福利厚生費の平均値は以下のとおりです。
| 法定福利厚生費 | 法定外福利厚生費 |
|---|---|
| 84,392円 | 24,125円 |
また、福利厚生の最低ラインは法定福利厚生の導入で、労働基準法で義務付けられている6種類を必ず導入する必要があります。
福利厚生を充実させる5つのメリット

福利厚生を充実させる5つのメリット
- 採用力の向上
- 社員の定着率の向上(離職率の低下)
- 生産性の向上
- 企業イメージなど社会的評価の向上
- 法人税の軽減
福利厚生の充実は、これらのメリットを通じて企業の競争力を高め、長期的な成長と安定を支える重要な要素となります。
詳しく見ていきましょう。
メリット1.採用力の向上
福利厚生が充実している企業は「守られている安心感がある」「この会社にいれば、メリットがたくさんある」と感じてもらいやすくなります。
特に家族を持つ社員にとっては、家族の健康や教育、将来に関するサポートが魅力的に映りやすく「会社を決める際の大きな決め手となる」といっても過言ではありません。
福利厚生で他社との差別化を図ることで、競争の激しい採用市場で企業の魅力が高まり、優秀な人材を引き寄せた結果、採用力の向上が期待できます。
メリット2.社員の定着率の向上
福利厚生が充実することで、社員の離職率が低下し、長期的な人材確保が可能です。
生活や健康に配慮された福利厚生を提供することで、社員の企業に対する満足度が向上し、「長く働き続けたい」という意欲が高まります。
また、福利厚生によって働きやすい環境が整うことで、日々の仕事へのモチベーションも向上し、業務パフォーマンスの改善にもつながります。
こうした好循環により、優秀な人材の流出防止だけでなく、社員の積極的な成長意欲も引き出せるのです。
メリット3.生産性の向上
健康管理やメンタルヘルスケアに関する福利厚生をそろえ、相談できる場を整えることで、社員はストレスを受けたときなど都度相談ができます。
一人で抱え込まずに早い段階で相談することで、心身の健康に必要なケアを受けることが可能です。
心身ともに健康なことで、仕事のパフォーマンスがあがり、生産性の向上が期待できます。
メリット4.企業イメージなど社会的評価の向上
福利厚生を充実させ「働きやすい職場」として社会的に認知されることで、顧客や取引先、求職者からの評価が向上し、企業のブランド価値やイメージ向上にもつながります。
社会的評価の向上に、顕彰制度を利用するのも一つの方法です。
例えば、経済産業省が実施している「健康経営優良法人認定制度」に認定されれば、「信頼できる企業だ」との評価を得ることが期待できます。
メリット5.法人税の軽減
福利厚生に充てた費用は、原則として「福利厚生費」として経費に計上できるため、法人税の負担を軽減することが可能です。
特に、社員全体に公平に提供される福利厚生サービスや手当は、経費として認められるケースが多く、節税効果を期待できます。
福利厚生の充実は、社員の満足度向上に貢献するだけでなく、企業の財務面でも有利な効果をもたらします。
福利厚生を充実させる3つのデメリット

福利厚生を充実させる3つのデメリット
- コストがかかる
- すべてのニーズには応えられない
- 管理に手間がかかる
上記の3つのデメリットは、企業が福利厚生を導入する際に慎重に検討する必要がある重要なポイントです。
詳しく見ていきましょう。
デメリット1.コストがかかる
福利厚生を充実させることで、企業の経費が増加します。
福利厚生を導入する際には、社員向けの各種プログラムやサービスを提供するための初期費用や運営費用が必要です。
特に中小企業では、これが財務的な負担となり、他の重要な投資に制約が生じる可能性もあります。
例えば、中小企業が社員の健康診断費用を全額負担する制度を導入した際、予想以上にコストがかかり、他の福利厚生の予算を削減せざるを得なくなる場合があります。
結果として、企業のキャッシュフローに影響が出て、当初予定していた設備投資を延期するなどの事態も考えられるため、段階的に導入することがおすすめです。
デメリット2.すべてのニーズには応えられない
福利厚生を充実させても、社員全員が満足するものを提供するのは難しく、一部の社員が不満を抱く可能性があります。
福利厚生にはさまざまな種類があり、社員のライフステージや個々のニーズにすべて対応するのは現実的に困難です。
その結果、特定の福利厚生が一部の社員にとって「魅力的でない」と感じられることがあります。
例えば、企業が育児支援を強化する福利厚生を導入した場合、子育て中の社員には好評な一方で、独身者や子どもがいない社員からは「自分には恩恵がない」と不公平感が生じる恐れがあります。
デメリット3.管理に手間がかかる
福利厚生の運用や管理には、多くの手間と時間がかかり担当者の業務負担の増加もデメリットです。
福利厚生プログラムを適切に運用するためには、さまざまな管理業務が必要となります。
- 社員の利用状況の把握
- サービス提供業者との連絡調整
- 法令遵守の確認
例えば、複数の福利厚生プログラムを同時に導入した場合、各プログラムの管理や社員からの問い合わせ対応に多くの時間がかかり、人事部門の負担が増えます。
負担が増えた結果、他の人事業務に支障が出たり、福利厚生の運用自体が効率的におこなえなくなったりする場合があるので、リソースは確保したうえで導入を検討しましょう。
福利厚生の導入で失敗しないための5つの注意点

福利厚生を導入する際に注意すべきポイントは次の5つです。
- 導入の目的を明確にする
- 従業員のニーズに合った内容を選ぶ
- 公平性を保つことを意識する
- 制度の内容を従業員にしっかり周知する
- 導入後も定期的に見直す
福利厚生は、導入目的を明確にし、従業員のニーズに合った内容を選ぶことで、効果を最大化できます。
また、公平性を保ちつつ、周知を徹底することで、社員全員が活用しやすい環境を整えることが重要です。
導入後も定期的に見直し、時代に合った制度に改善していくことが、長期的な成功につながります。
注意点の他にも、福利厚生を導入する際に押さえておきたいポイントを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
デメリットを解決できる!福利厚生にも使えるデジタルギフト

福利厚生にデジタルギフトを活用することで、前述したデメリットの解消が可能です。
デジタルギフトを福利厚生に使用する3つのメリット
- URLを送付するだけで贈れるので、発送にかかるコストを削減できる
- 交換先が多いので、受取手のニーズに応えやすい
- 在庫管理や事務手続きにかかる負担を削減できる
受け取った人は好きなものを購入できるため、社員のライフステージや個々のニーズに柔軟に対応できます。
福利厚生にデジタルギフトを導入している事例
- 周年記念や永年勤続表彰の記念品
- リモートワーク支援
- ピアボーナス(同僚からの評価に基づく報酬)
- 社内イベントの景品
- 交通費補助 など
デジタルギフトは、さまざまな福利厚生に適しており、管理や配布が簡単で、企業にとっても効率的に運用できる点が魅力です。
特にリモートワークや多様な働き方が広がるなかで、場所や時間に縛られずに利用できるデジタルギフトは、今後ますます重要な役割を果たすことが考えられます。
福利厚生にも使えるデジタルギフトの「デジコ」

福利厚生として手当や報酬制度でデジタルギフトを導入するなら、「デジコ」が使いやすくおすすめです。
デジタルギフトはオンラインで贈れるクーポンや割引券のことで、一例としてコンビニスイーツや各種ポイントに引き換えられます。
社内メールなどを通して簡単に贈れるため、現金のように振込手数料は発生しません。
デジコには以下の特徴があるため、福利厚生として使いやすくなっています。
デジコの特徴
- 最大6,000種類のギフトから従業員が好きなものを選べるので、選択肢が多く喜ばれやすい
- 導入後、CSV発注なら2時間以内で発券可能なので、スピーディに対応できる
- 1円からギフトを発行できるので、手当や報酬の額を調整しやすい
福利厚生の充実は、従業員満足度の向上につながります。
選択肢の多さから従業員に喜ばれやすく、柔軟な対応が可能なデジコの資料は、以下のボタンからダウンロードいただけます。
従業員に喜ばれる魅力的な福利厚生の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。デジコの資料をダウンロードするまた、福利厚生におすすめのギフトを知りたい場合は、こちらもあわせてご覧ください。
社員にとってあるとうれしい福利厚生とは

転職情報をまとめたメディア「ミライのお仕事」が、18歳以上の会社員経験がある男女400人へアンケートをおこなったところ、住宅に関するサポートを望む声が最も多く44.0%でした。

支出のなかでも、家賃などの住宅に関する費用の負担が大きく、昨今の物価高騰の影響もあって、住宅に関する補助を希望する社員が増えています。
その他、社員食堂やカフェ、ランチ費用補助などの食事に関する福利厚生も人気がありました。
社員が喜ぶ福利厚生を導入するためには、アンケートや調査を通じて社員の声を反映させることが効果的です。
具体的な福利厚生の事例が知りたい場合は、以下の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。
会社によって、喜ばれる福利厚生も変わってきます。スキルアップや休暇に関する福利厚生の事例を知りたい場合は、こちらもぜひご覧ください。
また、中小企業で人気の福利厚生ランキングを知りたい場合は、こちらをご覧ください。
まとめ:福利厚生にはさまざまな種類がある

福利厚生は法定福利厚生・法定外福利厚生の大きく2つに分類できます。
さらに細かく分けると、法律で定められた法定福利厚生は6種類、企業が独自に取り組める法定外福利厚生は12種類あるとお伝えしました。
従業員のニーズに合った福利厚生を導入することで、従業員の満足度や定着率の向上が期待できます。
ぜひ自社にあった福利厚生を検討して、長期的な成長につなげましょう。
とはいえ、どの福利厚生を取り入れるべきか迷っている企業も多いのではないでしょうか。
福利厚生のなかでも、デジタルギフトは手軽に導入でき、選択肢の多さから喜ばれやすいため、多くの企業で注目されています。
法人専用のデジタルギフトサービス「デジコ」は、最大6,000種類のなかから好きなギフトを選べるので、従業員に喜ばれやすいです。
また1円単位で贈れるため、予算を変えずに参加人数を増やすなど柔軟な運用もできます。
デジコの詳細は、サービス資料で詳しくご紹介していますので、以下のボタンからぜひダウンロードしてみてください。デジコの資料をダウンロードする








