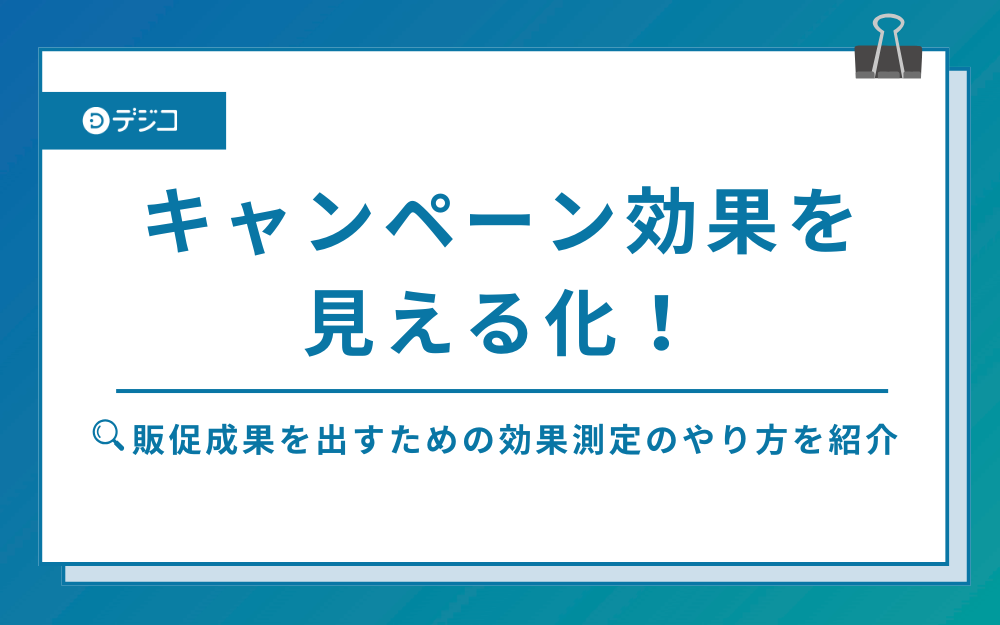.png)
販促計画は5ステップでOK!プロモーション効果を最大化する事例もあわせて紹介
何事も良い結果をもたらすには、入念な計画が大切です。
販促においても同じことがいえ、達成したい目標や施策を打ち出すタイミングなど、計画を立てて準備することが欠かせません。
とはいえ「どのように販促計画を立てれば良いかわからない」と、悩むこともあるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、販促計画の手順を5ステップで紹介します。
販促計画の進め方や検討項目がわかるため、ぜひ参考にしてください。
販促キャンペーン後の景品発送や在庫管理にかかるコストを削減するなら、デジタルギフトサービスの活用がおすすめです。
デジタルギフトなら、SNSやメールにURLを送付するだけで完結できるため、発送や在庫管理の手間がかかりません。
法人向けデジタルギフトサービス「デジコ」は導入実績1,600社以上あり、安心してご利用いただけるサービスです。
詳しくは以下のボタンより資料をご覧ください。
目次 []
販促計画とは

そもそも販促計画とは、商品・サービスの販売促進のために、どのような手法や取り組みをするか決めることです。
販促にはさまざまな方法があるため、やみくもに実施しても思うような結果につながりません。
あらかじめ販促計画を立てておけば、目的とブレのない施策や、最適なプロモーション方法を選べます。
販促とプロモーションの違いとは?
「販促」と「プロモーション」はどちらも似たような意味に見えますが、実は目的や範囲に違いがあります。
| 項目 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 販促 |
|
|
| プロモーション |
|
|
簡単にいうと、販促は「売るための施策」で、プロモーションは企業ブランディングや顧客との接点づくりも含めた「知ってもらう・つながるための施策」です。
「プロモーションのなかに販促が含まれる」と考えると、イメージしやすくなります。
ここからは「販促をより効果的に進めるために、なぜ「計画」が重要なのか」をみていきましょう。
計画的な販促活動がなぜ重要なのか?
販促は、その場のひらめきで動くよりも、しっかりと計画を立てて進めたほうがより高い効果が期待できます。
販促計画が重要な理由は、以下の3つです。

まず伝えたいのは「販促計画があると、役割分担が明確になる」という点です。
計画を立てれば「いつ・誰が・何をするのか」が明らかになるため、社内の連携はもちろん、外部パートナーとの調整もしやすくなり、施策の迷走を防げます。
あらかじめ優先順位を決めておけば、社内外の動きがブレなくなり、限られた予算や人手、時間をムダなく使えます。
必要なところにしっかりリソースを集中させられるのも、計画があるからこそです。
季節や流行に合わせた販促も、計画なしでは対応できません。
「この時期はこれが売れる」とわかっていれば、タイミングを逃さずアプローチできます。
商品やサービスが売れにくい時期(閑散期)の対策も販促計画に組み込んでおくことで、安定した売上づくりに貢献できます。
では、販促計画はどのようなステップで立てれば良いのでしょうか。
次の章では、5ステップで販促計画を立てる方法を具体的に紹介します。
販促計画を立てる手順を5ステップで解説

上記の順で計画を立てることで、本来期待している効果や目的を見失わずに販促を実施できます。
1ステップずつ、順番にみていきましょう。
1.現状を分析し課題を見つける
まずは商品販売に関する現状を分析し、販促で改善・成長させたい課題を明らかにしましょう。
売上を構成する要素から現状を分析すると、課題が見つかりやすくなります。
一例として、以下のような分析項目があります。
分析する項目の一例
- 売上高
- 客数
- 客単価
- 商品価格
- リピート率 など
分析に必要なデータを集めたら、
- 仮説を立てる
- 顧客のニーズを調べる
- 競合との比較をする
などをおこなって課題を見つけましょう。
2.販促をおこなう目的を明確にする
ステップ1で見つかった課題に沿って、販促の目的を決めます。
販促目的を明確にするには、「売上の構成要素(客数・客単価・購買頻度)のどこに課題があるか」を見極めることがおすすめです。
例えば客数が少ないのが課題の場合、「商品の認知度を上げて新規顧客を増やす」という目的が考えられます。
販促をおこなう目的は大きく以下の3つに絞れるため、どこを目指すと課題を克服できるか検討してみましょう。
- 認知の拡大
- 購入・消費の促進
- 既存顧客の維持(リピート)
3.達成したい目標を設定する
続いては、販促により達成したい目標を設定します。
目標は数値で設定するほうが効果検証がしやすく、かつ具体的な認識をもって取り組めます。
目標の例
- NG例「売上をアップする」
- OK例「リピーターを増やすために、アプリ会員を前期比125%にする」
売上目標があれば、「売上=客数×客単価×購買頻度」のどこがどのくらい不足しているか逆算し、目標数値を立てましょう。
4.ターゲットを設定する
次に目標達成に向けて、アプローチするターゲットを設定します。
明確なターゲット像があれば、どのようなエリアで販促するか、どのような施策が喜ばれるか考えやすくなります。
年齢・性別・居住エリア・職業など、さまざまな視点から顧客のセグメンテーションをおこないましょう。
5.販促計画表を作成する
ここまで決めた内容を、販促計画表や販促カレンダーに落とし込みます。
販促計画表は、季節のイベントや社内外行事を月別に表し、それにあわせて販促スケジュールをはめ込んでいきます。
販促計画表・販促カレンダーは、以下のようなイメージです。

販促計画表は、販促計画を一覧で確認でき、中長期的に施策を実施していくのに役立ちます。
販促計画表や販促カレンダーは自作でももちろんOKですが、始めはテンプレートに沿って作ると簡単なのでおすすめです。
販促計画でおさえたい5つの検討項目

販促計画の流れをお伝えしましたが、計画策定のなかでは検討すべき項目がいくつも浮かび上がります。
ここでは、販促計画の際に必ずおさえておきたい検討項目について紹介します。
1.販促・プロモーション手法
販促目的やターゲットにあわせて、実際にどのようなプロモーションをおこなうのか検討しましょう。
販促手法は非常にさまざまな種類があり、適切な手法を選ばないと期待する効果が得られません。
例えば、販促やキャンペーンをおこなう目的が「新規獲得」なのか「リピート促進」なのかで、使うべき販促手法は異なります。
ポイント還元やキャンペーンはリピートには効果があっても、新規獲得には刺さらないケースもあります。
販促やプロモーションの目的と手段がかみ合っていないと、目的は達成しにくいです。
主な販促手法とその目的を一覧にすると、以下のとおりです。
| 販促手法 | 販促目的 |
|---|---|
| マス広告 | 認知の拡大 購入・消費の促進 |
| 交通広告・デジタルサイネージ | 認知の拡大 購入・消費の促進 |
| インターネット広告 | 認知の拡大 購入・消費の促進 |
| SNS運用・SNSキャンペーン | 認知の拡大 購入・消費の促進 |
| サンプル配布・実演販売 | 購入・消費の促進 |
| 販促品 | 購入・消費の促進 |
| ポイントプログラム | 既存顧客の維持(リピート) |
| メルマガ | 既存顧客の維持(リピート) |
| 会員限定イベント | 既存顧客の維持(リピート) |
「販促・プロモーション手法がターゲットに合っているか?」という視点も大切です。
例えば若年層にはSNSキャンペーンが有効ですが、高齢者層には新聞折込やDMのほうが反応が良い場合もあります。
販促・プロモーション手法がターゲットの行動特性や情報接点と合っていないと、情報はターゲットまで届きません。
近年のトレンドでは、オンラインとオフラインを組み合わせた「O2O(Online to Offline)」のような施策が主流になっています。
例えば、QRコードを使って実店舗に誘導したり、NFCタグで商品情報を提供したりと、デジタルとリアルをつなぐ取り組みです。
オンラインコンテンツでは、拡散性のあるショート動画や、AI技術を活用したプロモーションも注目されています。
販促・キャンペーンの目的やターゲット、メディアの使い方にあわせて、最適な手法を選びましょう。
上記以外にも販促手法はあるため、さらに詳しく知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
2.販促品
商品・サービスの購入率を高めるためには、販促品を用意するのがおすすめです。
販促品とは、商品を購入した方やキャンペーン参加者にプレゼントするアイテムのことで、あるとないとでは、購入のハードルが大きく変わります。
文房具や生活雑貨などが代表的ですが、重要なのはターゲットにマッチしているかです。
例えば、以下のように相手の性別・年齢・趣味嗜好に合わせると、高い販促効果が期待できます。
- 若年層には、スマートフォン関連グッズや推し活に使えるアイテム
- シニア層には、使いやすさを重視した日用品や健康グッズ
販促の目的に応じて、アイテムを使い分けるのも一つの手です。
- 顧客に長く愛用してほしい→実用性の高いもの
- SNSで話題になってほしい→写真映えするユニークなグッズ
さらに近年では、物理的な品物に加えてメールで送付できる「デジタルギフト」も注目を集めています。
受け取った人が自分で好きな商品やポイントと交換できる「選べるギフト形式」は、相手の属性を問わずに幅広い世代に喜ばれるため重宝します。
おすすめの販促品や選ぶポイントなどは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
3.販促の予算
販促を実施するにあたって、予算との折り合いを付ける必要があります。
業界によって販促費・広告費は大きく異なります。
販促にかける予算をこれから検討する場合は、同じ業界の平均値を参考にしてみましょう。
業界別の費用感については、次のデータが参考になります。
限られた予算のなかで効果を最大限にするには、コストパフォーマンスを上げる工夫も大切です。
コストパフォーマンスの向上には、次のような方法も検討してみてください。
予算内で効果的に販促をする方法例
- 今までの傾向から効果のある販促手法に絞る
- SNSを有効活用する
- エリア・ターゲットを限定する
4.販促の実施時期
何月何日に、どのくらいの期間にわたって販促を実施するか検討します。
販促の実施時期は、年間スケジュールの大枠から月間・週間の細かい期間へと落とし込みましょう。
チョコレートの販促例
季節のイベント:バレンタイン
実施時期:1月中旬~2/14に展示会・フェアに参加する、バレンタイン2週間前からSNSキャンペーンを実施する
スケジュールに沿った販促のほか、臨時の販促施策をあらかじめ計画しておくことも重要です。
販促の臨時施策は、SNSでバズったタイミングや、気候変化で商品の需要が高まりそうなときの実施がおすすめです。
販促の臨時施策例
- 「〇万いいね達成記念キャンペーン」として、感謝を込めてフォロワー限定クーポンを配布
- バズった投稿に関連する商品をピックアップし、「話題の商品セット」を限定販売
- 「バスり記念プレゼント企画」として、RT・いいねした人から抽選で商品プレゼント
- ストーリーズやライブ配信で「今見てくれた人だけ特別割引」などのリアルタイム施策
- 急な気温上昇で需要が高まりそうなアイテムを対象に「週末限定クーポン」を配布 など
多くの人が自社アカウントを見に来てくれるタイミングのため、チャンスを活かして顧客獲得につなげましょう。
5.効果測定の方法
販促は実施するだけでなく、効果測定や分析までおこないましょう。
今回の販促で得られた結果は、次回の施策をブラッシュアップするための貴重なデータとなります。
測定する主な項目として、売上効果とコミュニケーション効果の大きく2種類あります。
| 項目 | 内容 | 効果の指標例 |
|---|---|---|
| 売上効果 | 販促によって売上がどのように変化したかを分析する | 販促を打ち出した前後の売上高 |
| コミュニケーション効果 | 消費者が起こした行動から販促の効果を分析する | クーポン配布枚数に対する来店者数の増減 |
それぞれの効果測定方法や分析時の注意点については、以下の記事で詳しく紹介しています。
こちらもぜひ参考にしてください。
デジコでは、ここまで紹介してきたステップやポイントをわかりやすくまとめた資料を用意しています。
販促キャンペーンを企画する方は、悩んだときのヒントとしてお手元でご活用ください。販促キャンペーンの資料をダウンロードする
販促・プロモーションプランの参考にしたい事例5選

販促やプロモーションには、さまざまな手法があります。
販促やプロモーションで成果を上げるためには、「誰に届けるのか」「何を伝えたいのか」にあわせて、最適な手法を選ぶことが大切です。
ここでは、実際に成果を上げた5つのプロモーション事例を紹介します。
販促・プロモーションプランの参考にしたい事例5選
- 株式会社中央ツーリスト
- 楽天グループ株式会社
- 株式会社丸亀製麺
- 株式会社カインズ
- アトム法律事務所
1.株式会社中央ツーリスト

沖縄県の老舗旅行代理店「株式会社中央ツーリスト」では、従来の店頭キャンペーンからWeb中心の販促へと切り替えを進め、成功しています。
同社は、来店者数の減少や、キャッシュバック施策における個人情報の取り扱いなど、従来の方法に課題を感じていました。
そこで導入したのが、デジタルギフトサービス「デジコ」を活用したWebキャンペーンです。
取得する顧客情報はメールアドレスだけで済むため、管理負担が軽減しました。加えて、推したい商品にポイントを集中させることで、販売の後押しにもつながりました。
具体的な施策に関して詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
参考:株式会社中央ツーリスト様
2.楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が運営する「楽天トラベル」では、宿にいる看板犬を主役にしたユニークな企画が注目を集めています。
11月1日の「犬の日」にちなんで全国の宿における看板犬の日本一を決定する「楽天トラベル 全国の宿 自慢の看板犬ランキング」を発表し、ランクインした宿の紹介をしています。
「犬の魅力」から宿を選ぶという推し活感覚で宿を選べる斬新な仕組みが、多くのユーザーの心をつかみました。
3.株式会社丸亀製麺

株式会社丸亀製麺は、時代の変化にあわせたプロモーションプランを展開しており、人気が絶えません。
例えば、2020年に独自ハッシュタグ「#丸亀製麺さん暑いです」を使ったX(旧:Twitter)キャンペーンでは、2.4万リポストを獲得でき、拡散力のあるプロモーションとして成功しました。
\13時まで!/
抽選1000名様!#氷うどん か #冷かけ の【無料】クーポン当たる🎐
条件は
①@UdonMarugameをフォロー
②この投稿に #丸亀製麺さん暑いです とあなたの「熱い気持ちで推している事」をつけて時間内⏰にコメント付きリツイート🔁
③結果が届く🎉
8月4日13:00迄 pic.twitter.com/7gVZ4H5h38— 丸亀製麺【公式】 (@UdonMarugame) August 3, 2020
子どもたちに食の楽しさを伝える「食育活動」にも積極的で、一部店舗ではうどん教室を開催するなど、社会貢献にも力を入れています。
4.株式会社カインズ

オウンドメディアの運用で認知度を高めているのは、ホームセンター大手の株式会社カインズです。
「ホームセンターを遊び倒すメディア」をコンセプトとしたオウンドメディア「となりのカインズさん」では、暮らしに役立つ情報をメインに発信しています。
例えば、以下のような読者の暮らしに寄り添うコンテンツが好評です。
- オキシクリーンでスニーカーとお風呂を新品同様にする「オキシ漬け」の方法
- 一人暮らしの人が持つべき「防災意識」と「グッズ」について専門家に聞いてみた
- 春からはじめる火を使わない「1週間お弁当レシピ」。とにかく簡単に作りたいを解消!
5.アトム法律事務所

最後に紹介するのが、YouTubeを活用して認知を広げた事例です。
上記のチャンネルは、現職の弁護士が法律に関するさまざまな質問や疑問に答える内容で、チャンネル登録者数は175万人と業界でも異例の人気を誇っています。
YouTubeだけでなくTikTokでも多数の賞を受賞しています。
- TikTok AWARD 教育部門 最優秀賞(2022・2023年)
- YouTube FanFest 国内ショート動画ランキング第1位(2021)
- TikTok AWARD ティーチャー部門 最優秀賞(2021)
法律という一見難しそうな「堅い分野」でも「伝え方を工夫すれば、多くの共感と拡散を生み出せる」ことを示す好例です。
ここまでで、業種も手法も異なる5つの販促・プロモーション事例をご紹介しました。
どの事例にも共通していたのは「ターゲットや時代に合わせた柔軟な対応」です。
まずは小さくスタートして反応をみたり、SNSやデジタルギフトを取り入れるだけでも、販促の幅はぐっと広がります。
ぜひご自身の販促計画づくりの参考にしてみてください。
魅力的な販促品があると、参加者が集まりやすくキャンペーンが成功しやすいです。
ここからは、ユーザーからの反応が良く喜ばれやすい販促品を紹介します。
販促キャンペーンで反応が良い販促品はデジタルギフト

販促品には、クーポンや文房具、生活雑貨などさまざまな種類がありますが、デジコがおこなったデジタルギフトに関する調査では「販促キャンペーンなどで反響がよかったギフト」としてデジタルギフトが挙げられています。
以下の画像は、販促などで反応の良かった景品をグラフでまとめたものです。

本調査の詳細は、以下の記事にまとめています。
独自調査の結果をグラフも交えながら紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
デジタルギフトは、受け取り手が好きなプレゼントを選べるため、年齢・性別問わず幅広い人に喜ばれやすく、販促品に最適です。
販促でデジタルギフトを活用したい場合は、運用しやすい仕組みやサポートが充実している法人専用のサービスがおすすめです。
ここからは、法人専用のデジタルギフト「デジコ」を紹介します。
販促品なら法人向けデジタルギフト「デジコ」がおすすめ

販促でデジタルギフトを使うなら、ラインナップが豊富でかつ法人向けのサポートや機能が充実している「デジコ」がおすすめです。
デジコは法人向けデジタルギフトサービスで、これまで1,600社以上の会社で導入されています。
デジコの特徴
- 最大6,000種類の豊富なギフトラインナップ
- 導入後、CSV発注なら2時間以内で発券可能
- メールアドレスのみでギフトが贈れるため個人情報の管理が最小限
- 無料API連携でギフト発行の自動化ができ、業務効率化が実現
最大6,000種類の豊富なラインナップがあるため、受け取り手の満足度も高く、喜ばれやすい販促品として活用できます。
郵送費や銀行振込費などのコストだけではなく、無料API連携を活用した業務効率化など、人的コストの削減にもつながるデジコの概要については、以下のボタンよりダウンロードいただけます。
デジタルギフトを活用して販促キャンペーンを成功させたい方は、お気軽にダウンロードください。
まとめ:計画的な販促がプロモーション成功の近道

販促の効果を得るためには、計画的に準備を進めることが大切です。
プロモーション方法や予算の策定、効果検証などもおこない販促成功へとつなげましょう。
販促の景品には、汎用性が高く、参加者に喜ばれやすいデジタルギフトサービスの活用がおすすめです。
デジタルギフトは、少額から気軽に贈れるうえSNSやメールでURLを送付するだけで完結するため、発送や在庫管理の手間がかかりません。
法人向けデジタルギフトサービス「デジコ」は、導入実績1,000社以上あり、安心してご利用いただけるサービスです。
デジコの詳細は、以下のボタンより資料をダウンロードのうえご覧ください。デジコの資料をダウンロードする