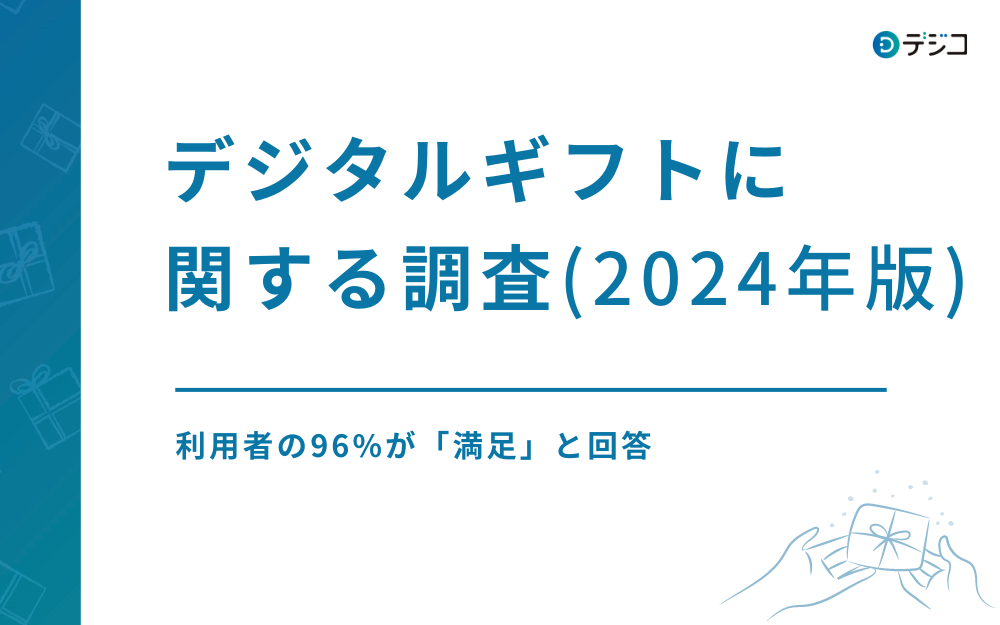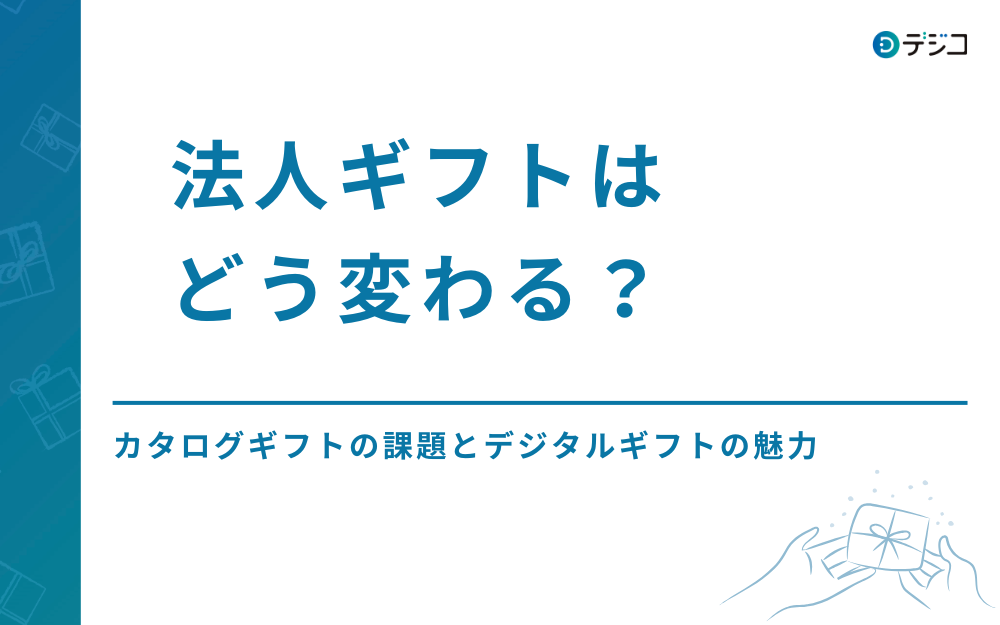
法人ギフトはどう変わる?カタログギフトの課題とデジタルギフトの魅力
取引先へのお礼や社内表彰など、法人ギフトで長く選ばれてきたのがカタログギフトです。
受け取った人が自由に商品を選べるため「ギフトを気に入ってもらえないかもしれない」などの不安なく贈ることができ、使い勝手が良いと支持されてきました。
その一方で、カタログギフトには、配送や在庫管理のコストがかかるなどのデメリットもあります。
そこで近年注目が集まっているのが、贈られた側が自由に選べる良さを持ちつつ、オンラインで手軽に贈れてコスト削減も期待できるデジタルギフトです。
本記事では、法人がギフトを選ぶ際に押さえておきたいカタログギフトの強みと課題、デジタルギフトの特徴を整理し、用途に応じた選び方を紹介します。
受け取った人が自由に商品を選べるデジタルギフトは、ユーザーから「欲しい!」と思われやすく、キャンペーンの景品など販促の施策にも適しています。
法人向けデジタルギフトサービス「デジコ」なら、最大6,000種類のアイテムから好きなギフトに交換可能です。
幅広い層に喜ばれやすく、施策の効果アップが期待できるデジコの詳細は、以下から資料をダウンロードしてご確認ください。
目次 []
法人ギフトにカタログギフトが選ばれる3つの理由

法人ギフトにカタログギフトが選ばれる3つの理由
- 相手の好みを知らなくても安心して贈れる
- 贈り手・受け取り手双方にメリットがある
- フォーマルなシーンにも適している
取引先へのお礼や社内表彰などで贈る法人ギフトでは、相手に失礼なく喜んでもらうことが重要です。
カタログギフトが選ばれる理由をみていきましょう。
1.相手の好みを知らなくても安心して贈れる
法人の贈答でカタログギフトが選ばれる最大の理由は、贈った相手が自分で好きなものを選べるため、嗜好を知らなくても贈りやすいことです。
カタログギフトを選べば、以下のような取引先にも迷わず贈れます。
- 食の好みがまったくわからない
- おしゃれでセンスが問われそう
- 家族構成やライフスタイルがわからない など
カタログギフトは、相手にとって失礼にあたるアイテムを選んだり、期待に添えずがっかりされたり、ということが起こりにくいため、担当者にとっても採用しやすいギフトです。
2.贈り手・受け取り手双方にメリットがある
カタログギフトは、受け取り手が自分で好きな商品を選べるため、満足度が高まりやすい点も大きな魅力です。
例えば、贈り手にとっては以下のメリットがあります。
- 受け取り手に喜んでもらいやすい
- 商品選びに使う時間を削減できる
- 予算管理がしやすい
- かさばらないので配送費コストを削減できる
受け取り手のメリットは、以下です。
- 欲しいものが手に入る
- 選ぶ楽しみがある
- 選んだ商品を持ち運ぶ手間がない
- 好みではないものをもらった時の罪悪感がない
このようにカタログギフトは、贈り手と受け取り手双方にメリットがあります。
結果として、ギフトを贈った後に良い関係を築きやすく、顧客や従業員との関係性の維持・強化にもつながりやすくなります。
3.フォーマルなシーンにも適している
法人ギフトは、企業そのものの印象を左右するため、フォーマルなシーンでは体裁や格式を整えることが重要です。
カタログギフトには1万円以上の高額コースも多く、箱に入れて包装してもらえる商品も多くあるため、取引先へのお礼や社内表彰、周年記念といったフォーマルな場面にも対応できます。
さらに、冊子やカードを実物として手渡しできるため、セレモニーの場で贈る行為そのものをきちんと演出できます。
このように、カタログギフトは、法人のさまざまなシーンで安心して使えるギフトの定番として支持されてきました。
一方で、カタログギフトの運用にあたっては、事前に確認しておきたい注意点と課題があります。
次の章で確認していきましょう。
法人でカタログギフトを使う際の3つの注意点と課題

法人でカタログギフトを使う際の注意点と課題
- 配送や在庫管理のコストがかかる
- 紙カタログは環境配慮の面で課題がある
- 受け取り手の手間がかかる
大切な場面で使うギフトだからこそ、注意点や課題を踏まえたうえで贈るのが望ましいです。
詳しく解説しますので、ぜひチェックしてください。
1.配送や在庫管理のコストがかかる
カタログギフトは、冊子やカードを物理的に発送するため、1件ごとに送料が発生します。
カタログギフトを全国へ大量配布する際は、トータルコストが膨らみやすい点は否めません。
宅配便などを利用して発注する際は、納品まで数日を要するケースが多く、即日に商品を届けることも難しいです。
他にも、社内でカタログ冊子やカードを保管する場合は、スペースの確保や在庫管理の手間も発生します。
効率性を重視する法人利用では、コスト・工数の負担になりやすいことが課題です。
2.紙カタログは環境配慮の面で課題がある
紙カタログは、印刷・輸送・廃棄の各段階で資源消費やごみの発生につながります。
処分が必要な紙中心のギフトは、受け取り手がSDGsやCSRを積極的に掲げている場合、方針に合わない印象を与える可能性があります。
カタログギフトは贈り物としての体裁が整っているというメリットがある一方で、環境配慮を重視する取引先や顧客に贈る際は、不向きな場合があることは否定できません。
3.受け取り手の手間がかかる
カタログギフトは、ギフトを受け取る際に、はがき投函やWeb申し込みなどのアクションが必須です。
そのため忙しい方や申し込み期限を失念した方は、ギフトを受け取れないケースがあります。
万が一ギフトを受け取ってもらえなかった場合、感謝の気持ちが十分に伝わらず、期待していた関係構築の効果も得られません。
カタログギフトには確かなメリットがある一方、コストや受け取り手の負担といった課題も残ります。
これらの課題を補える仕組みとして、近年広がっているのが「デジタルギフト」です。
次の章ではカタログギフトとデジタルギフトの両者を比較し、目的・条件に応じた選び方を整理します。
法人ギフトはどう変わる?カタログギフトとデジタルギフトの比較

従来のカタログギフトと比較しながら、それぞれに適した場面を表にしました。
| 項目 | カタログギフト | デジタルギフト |
|---|---|---|
| 贈り方 |
|
|
| コスト |
|
|
| 環境面 |
|
|
| 受け取りやすさ |
|
|
カタログギフトは、フォーマルな贈答や冊子を手に取る体験を重視したい場面に適しています。
一方、スピードや運用効率が求められるシーンで力を発揮するのがデジタルギフトです。
どちらが優れているかではなく、目的や相手に応じて適材適所で使い分けるのがおすすめです。
次の章では、デジタルギフトを使いたい場合に、どのように活用されているのかをみていきましょう。
法人がデジタルギフトを活用するシーン

デジタルギフトは、配布スピードや利便性を活かして法人のさまざまなシーンで利用できます。
法人がデジタルギフトを活用しやすいシーンは、以下のとおりです。
- スピーディな対応が求められる表彰
- 参加率を高めたい調査
- 効率性が重要なキャンペーン
なかでも、特にデジタルギフトのメリットを発揮しやすい具体的な活用場面は次の3つです。
- 社内表彰・インセンティブ: 当日配布ができ、社員の満足度を高められる
- アンケートやモニター調査の謝礼: その場で受け取れるため参加意欲や回収率が向上する
- 顧客向けキャンペーンの景品: 大量配布に対応し、コストを抑えて全国規模の施策にも活用できる
従来のカタログギフトでは実現しづらかったスピードと利便性があるデジタルギフトは、参加率向上・大規模配布など法人の施策に直結する場面で力を発揮します。
利用者400名を対象としたデジタルギフトに関する調査でも、利用者の96%がデジタルギフトに満足と回答しています。
他にもデジタルギフトとリアルギフト(有形)の運用面での比較など、デジタルギフトに関する興味深い調査結果を紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。
便利で多様なサービスが増えているデジタルギフトは、法人利用においても選択肢が着実に広がっています。
とはいえ、実際に導入を決める段階では、どのサービスを選ぶべきか迷うこともあるのではないでしょうか。
そこで、次の章ではデジタルギフトを選ぶ際のポイントをわかりやすくご紹介します。
デジタルギフトを選ぶ4つのポイント

デジタルギフトを選ぶ4つのポイント
- ラインナップの豊富さ
- 配布スピードと手軽さ
- 法人対応・機能の手厚さ
- コストのわかりやすさ
それぞれのデジタルギフトには特徴があるため、サービスごとの特徴を踏まえ、自社に合うかを見極めることが重要です。
4つのポイントを詳しくみていきましょう。
1.ラインナップの豊富さ
法人ギフトは、取引先・社員・顧客など受け取り手が多様で、好みもさまざまです。
そのためデジタルギフトを選ぶ際は、幅広い商品ジャンルを網羅しているかが重要になります。
例えば、AmazonギフトカードやApple Gift Cardといった汎用性の高いギフトに加え、飲食・エンタメ・生活用品まで用途別に選べる選択肢がそろっていると、多様なニーズに応えることができ安心です。
ギフトのバリエーションが多いほど、相手の好みに合わない可能性が減り、満足度の向上につながります。
2.配布スピードと手軽さ
表彰や謝礼などすぐにギフトを渡したい場面では、当日配布に対応できるかがポイントです。
URLやメールで送付できる形式なら、遠方の相手や大人数への一斉配布もスムーズにおこなえます。
デジタルギフトは、紙の冊子のように在庫や配送手配が不要です。
そのため、担当者の工数や発注から配布までの時間を大幅に削減でき、短期の施策でもタイミングを逃さずに実施できます。
3.法人対応・機能の手厚さ
法人ギフトとして安心して導入できるかは、法人向け機能が整っているかで決まります。
例えば、請求書払いに対応していれば、経理処理や社内決算のフローがスムーズです。
さらに、配布履歴をデータで管理できる機能があれば、「誰に・いくら・いつ配ったか」を即座に把握でき、運用効率が大きく高まります。
加えて、専用のサポート窓口があると、万が一のトラブルや不明点にも迅速に対応してもらえるため安心です。
こうした法人特有のニーズへの対応は、安心感だけでなく、運用の効率化や施策の信頼性にも直結する重要ポイントといえます。
4.コストのわかりやすさ
デジタルギフトの導入時に忘れずに確認したいのが、コスト構造のわかりやすさです。
初期費用や月額固定費がかからず、発注した分だけ請求のシンプルな料金体系であれば、安心して利用できます。
隠れた手数料(発行手数料・最低発注額・キャンセル料など)の有無も、コストを考える上で重要なチェックポイントなので、必ずチェックしましょう。
料金体系がシンプルなサービスだと、コスト管理がしやすいため、導入後の運用が安定し長期的にも無駄のない活用ができます。
次の章では、これら4つのポイントを満たし、すでに多くの企業に選ばれている法人専用のサービスをご紹介します。
法人で使うデジタルギフトはデジコがおすすめ

デジコは、法人専門のデジタルギフトサービスです。
法人ギフトで求められる安心感と運用のしやすさを両立しているため、1,600社以上に導入されています。
デジコの特徴
- 導入費用や月額は無料で、発注した分だけ請求のわかりやすい料金設定
- 導入後、CSV発注なら2時間以内で発券可能
- 最大6,000種類のデジタルギフトから自由に選べる
- 請求書払いなど法人向け機能が充実
これらの特徴により、デジコは「コストを抑えつつスピーディーに贈れる」法人ギフトとして、多くの企業に選ばれています。
導入コストが抑えられ、さらに導入後に運用の効率化もできる点が、デジコの大きな魅力です。
デジコの具体的なサービス内容や導入事例を知りたい方は、以下の資料をご覧ください。
まとめ:法人ギフトは「選べる安心」に加えて「効率」も重視する時代へ

今まで定番だったカタログギフトに加えて、効率性や利便性を備えたデジタルギフトの活用が広がっています。
ギフトの用途に応じて、カタログギフトとデジタルギフトどちらが適しているか、検討しましょう。
スピード重視のキャンペーンやインセンティブ、大量配布が必要な場合は、効率よく運用でき、URLの送付で配布できるデジタルギフトがおすすめです。
なかでも法人専門のデジタルギフト「デジコ」は、導入費用や月額は無料なので導入しやすく、1,600社以上の企業に導入されています。
API連携も無料で使えるため、ギフトの一括送付も可能です。
デジコの導入事例や詳細な機能はサービス資料にまとめていますので、法人ギフトをより効率的に運用したい方は、資料をダウンロードのうえご確認ください。