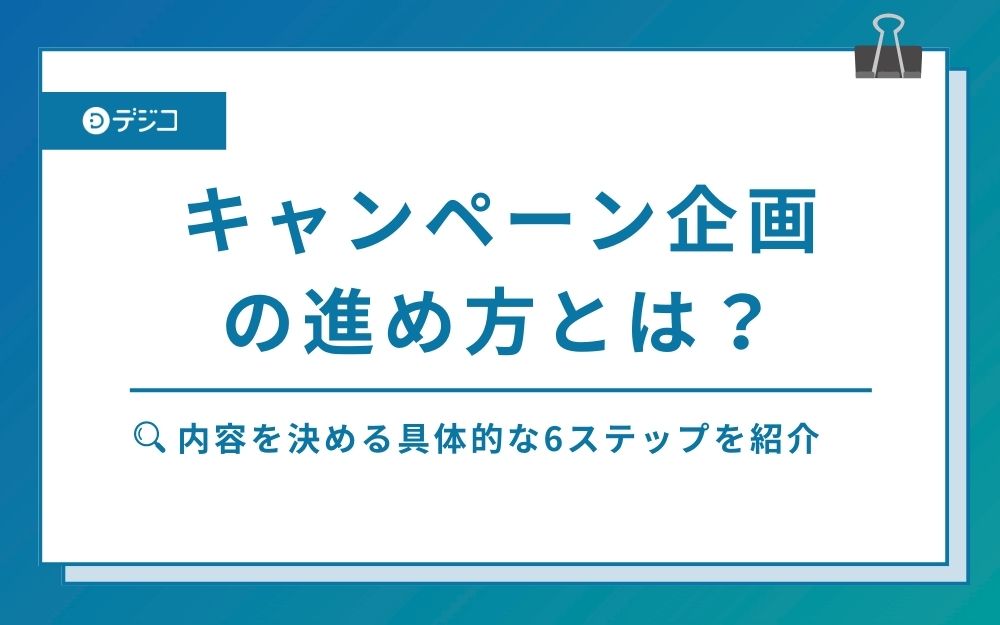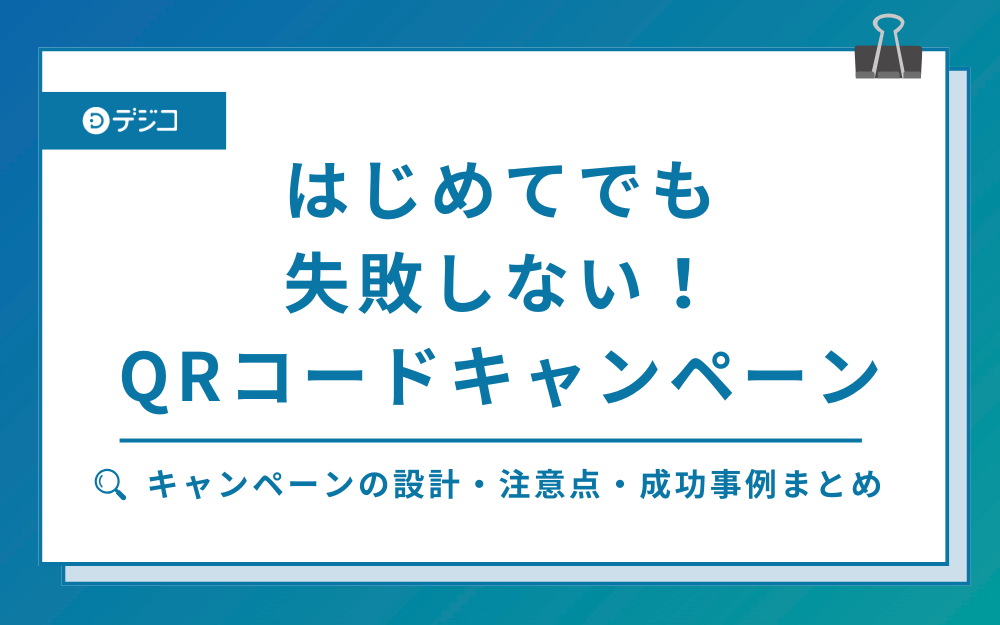
はじめてでも失敗しない!QRコードキャンペーンの設計・注意点・成功事例まとめ
QRコードを使ったキャンペーンは「スマートフォンから簡単に参加できる」というメリットがある一方で、サイズや読み取り環境によって「うまく読み取れない」「離脱率が高い」といった課題も生じがちです。
「せっかくおもしろいキャンペーンを企画したのに成果に結びつかない」とならないためにも、QRコードを活用したキャンペーンを実施する際は押さえておきたいポイントがあります。
そこで本記事では、はじめてQRコードキャンペーンを企画する方もすぐ実践できるよう、仕組みや準備の流れ、注意点、成功事例までをまとめました。
QRコードキャンペーンで来店や購入促進につなげたい方は、最後までご覧ください。
キャンペーンの景品には、デジタルギフトサービスの「デジコ」が役立ちます。
デジコは最大6,000種類の交換先から参加者が好きなギフトを自由に選べるので、幅広いターゲットに喜ばれやすいです。
法人専用サービスのため、API連携による自動発券や1円単位での発行など、企業側の運用コストや手間を抑えられる機能もそろっています。
デジコの詳細は、以下のサービス資料をダウンロードのうえご確認ください。
目次 []
QRコードキャンペーンとは?

QRコードキャンペーンとは、商品の購入やサービス利用を促進するため、QRコードを活用する販促手法です。
スマートフォンでQRコードを読み取るだけで、応募やアンケート回答、LINE友だち登録などのページへ簡単にたどりつけます。
QRコードキャンペーンは、紙の応募用紙を用意する必要がなく非接触・非対面で参加できるため、リアル店舗でもオンラインでも幅広い活用が可能です。
QRコードキャンペーンでは「ユーザーはどのように動くのか」などの行動フローを把握しておくことで、離脱ポイントや改善すべき導線が見えやすくなり、より効果的なキャンペーン設計につながります。
ここからは、ユーザーが実際にどのような流れでキャンペーンに参加するのかを、わかりやすく説明します。
QRコードを使ったキャンペーンでのユーザーの動き
QRコードキャンペーンにおける主な参加の流れは、以下です。
QRコードキャンペーンのユーザーの動き
- スマートフォンでQRコードを読み取り
- 応募ページにアクセス
- 応募・抽選・アンケート回答・LINE友達登録などで参加完了
- その場で抽選結果表示、または後日連絡
- 応募後、景品受取やポイント付与などの特典が届く
抽選結果の見せ方は、目的にあわせて選べます。
すぐに結果がわかる即時抽選型にすれば、イベント会場での参加者の盛り上がりを作りやすく、SNSシェアにもつながります。
一方で後日ポイント付与型や抽選型は、購入者限定ポイントや来店後の抽選参加など、条件達成を促したいときに効果的です。
目的やターゲットに応じて仕組みを使い分けると、より効果的なキャンペーンが設計できます。
「とはいえ、QRコードキャンペーンで気をつけなければいけないことってないの?」と気になる方もいるのではないでしょうか?
次は、QRコードキャンペーンの具体的なメリットとデメリットを紹介します。
押さえておきたい!QRコードキャンペーンのメリット・デメリット

QRコードキャンペーンには、運営側・ユーザー側ともにメリットとデメリットがあります。
活用前に知っておくべきポイントを、以下に整理しました。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 運営側 |
|
|
| ユーザー側 |
|
|
それぞれ、ひとつずつ解説します。
運営側のメリット・デメリット
QRコードキャンペーンをおこなう一番のメリットは、運営の負担を減らせる点です。
QRコードを使えば、店頭のPOPやレシートにQRコードを印刷するだけで応募受付ができます。
そのため応募用紙の配布や対面での対応が不要になり、コスト削減につながります。
応募時のアンケート情報や参加データもすべてデジタル化できるため、集計や分析も簡単です。
一方デメリットは、キャンペーンの仕組み作りを整えるのに時間がかかる点です。
QRコードキャンペーンは、QRコードを読み取ったあと、どこに遷移させるのか(応募フォーム、LINE登録、LPなど)を明確にし、ユーザーが迷わず行動できるような設計が必須になります。
そのため、システムやツールの選定、応募ページの作成、抽選システム、ツールによる不正対策などの準備で時間を要すため、キャンペーンの開始に一定期間かかるケースが多いです。
ユーザー側のメリット・デメリット
QRコードキャンペーンは、参加するユーザーにとってもメリットがあります。
ユーザーにとって特に魅力的なのは、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで、すぐに応募や抽選に参加できる手軽さです。
アプリのダウンロードや面倒な会員登録、紙の記入が不要なため、ストレスなく手続きを完了できます。
デメリットとしては、QRコードの読み取りが必要になるため、スマートフォンの操作に不慣れな方には参加が難しいことです。
スマートフォンを使い慣れていないターゲットにとっては、従来の紙の応募や店頭対応の方が反応が良いケースもあります。
このように、QRコードキャンペーンは効率よく参加を促せる一方で、ターゲット層によって向き不向きがあります。
そのため事前に「QRコードの活用はターゲットにとってメリットとなるか」を検討しておきましょう。
今すぐできる!QRコードキャンペーンの流れ3ステップ
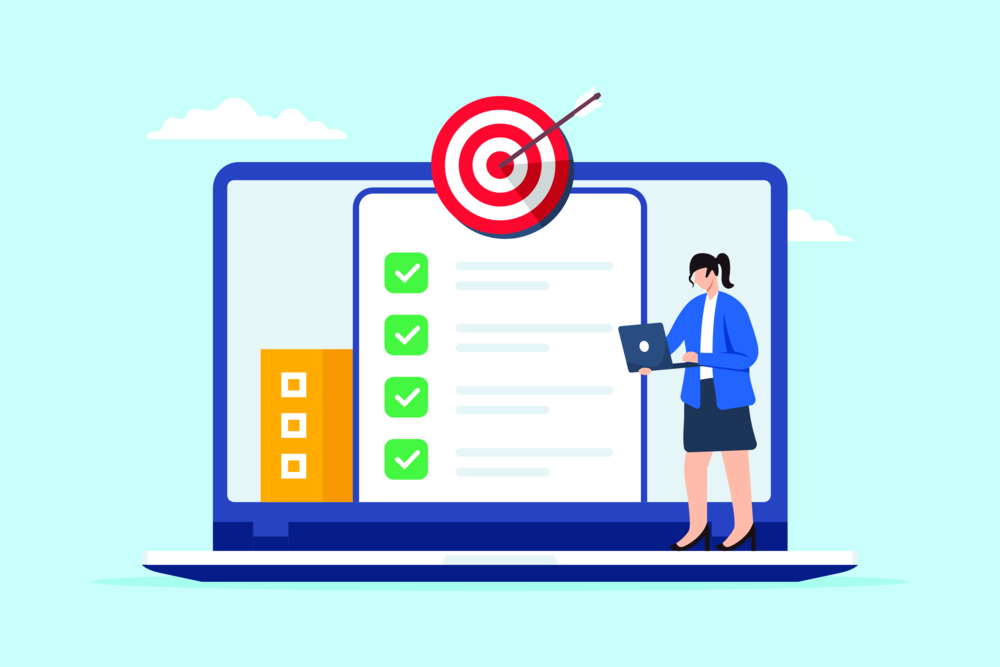
QRコードキャンペーンは、手順がシンプルで導入しやすいのが魅力です。
すぐ実践できるよう、企画から実施までの流れを3ステップで紹介します。
QRコードキャンペーンの流れ3ステップ
- キャンペーン内容の設計
- QRコードの作成と配置
- 応募完了後の対応・インセンティブ付与
キャンペーンの流れを把握することで、どこでユーザーが離脱しやすいかなどを事前に予測・改善できます。
ぜひチェックしてみてください。
1.キャンペーン内容の設計
最初のステップは、キャンペーンの目的と構成をしっかり決めることです。
設計は、以下3つの順に整理し決定していきます。
キャンペーン内容の設計
- 目的の設定
- 応募条件の設定
- 景品の決定
細かくみていきましょう。
1.目的の設計
設計をするうえで最も重要なのが、なんのためにキャンペーンをおこなうのか、という目的の確認です。
例えば、目的には以下のような種類があります。
- 認知拡大:SNS拡散を通じて商品やブランドを広めたい
- 集客:店舗やECサイトへの来店・来訪者数を増やしたい
- リピート促進:既存顧客のリピート・再購入を促進したい
目的が曖昧なまま始めると、キャンペーンの手法がぶれて効果が出にくくなります。
キャンペーンを設計する際には、必ず目的を確認して達成したいゴールを明確にしましょう。
目的とあわせて「目的達成ができたか」を測るための指標(KPI)も決めておくと、運用後の振り返りがしやすくなります。
以下は、目的別の指標例です。
| 認知拡大 SNS上での拡散力を可視化できる指標 |
|
|---|---|
| 集客 店やサイトに「足を運んでもらえたか」を測る指標 |
|
| リピート促進 短期の成果だけでなく、中長期視点の評価 |
|
2.応募条件の設定
目的を定めたら、応募条件を設定します。
応募条件は、参加者にどのような行動をとってほしいか、に直結させて考えると効果につながりやすいです。
目的別の応募条件例は、以下になります。
| 認知拡大 | 新聞や雑誌などに設置されたQRコードをスキャン ↓ 特設LPに遷移 ↓ X(旧:Twitter)リポストで応募完了 |
|---|---|
| 集客 | 店頭に設置されたQRコードをスキャン ↓ LINEミニアプリなどで「その場で当たる抽選」に参加 ↓ 景品・クーポンを獲得 |
| リピート促進 | 商品に同梱された専用QRコードをスキャン ↓ 次回購入時に使えるクーポンがもらえる・抽選に応募可能 |
条件が複雑・面倒だと参加率が下がるため、参加条件は手軽に参加できるように心がけましょう。
3.景品の設定
景品選びは、単に高額・豪華にすれば良いというものではなく、ターゲットにとって魅力ある景品であるかどうかがポイントです。
ニーズの高い景品であれば、参加率も自然と高まります。
目的別の景品例を、以下に挙げてみました。
| 認知拡大 | オリジナルグッズ、ギフトカード、試供品など |
|---|---|
| 集客 | 店頭でもらえるノベルティ、割引クーポンなど |
| リピート促進 | 次回使えるクーポン 割引クーポン、ポイント付与など |
参加率をさらに高めたい場合は、参加者がすぐに満足感を得られる景品を選ぶのが効果的です。
例えば、アンケート回答後すぐに受け取れるデジタルギフトは、参加者に喜ばれやすく、満足度の向上につながります。
以上がキャンペーンを設計する際の手順です。
「何のためのキャンペーンか」「どのような参加条件か」「どの景品なら響くか」を整理しながら設計すると、成果が出やすくなります。
キャンペーンの準備から終了後の流れまで企画手順を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご一読ください。
2.QRコードの作成と配置
キャンペーンの内容が決まったら、次はQRコードを作成し、読み取りやすい場所に配置します。
まず、誘導先となる応募ページやLINE公式アカウントを準備します。
特設ページや簡単な応募フォームでも問題ありませんが、ほとんどの方がスマートフォンで読み取るため、スマートフォンに最適化された画面を用意するのがポイントです。
次に、誘導先となるページのQRコードを生成します。
作成したQRコードのデザインは、読み取りやすいサイズ・デザインに工夫し、読み取り不良を防ぎましょう。
読み取りやすいポイントは、後述する「1.QRコードを読み取りやすいデザインにする」をチェックしてみてください。
印刷したQRコードは、参加者が自然に目にする場所へ設置します。
印刷したQRコードを配置する場所
- 店頭POPやレジ横のチラシ
- デジタルサイネージ
- SNS広告やWebサイトのバナー
- イベント会場のブース
視認性の高い場所に設置し、「今すぐ参加」「特典ゲット」など短い説明文を添えると、参加率がさらに向上します。
3.応募完了後の対応・インセンティブ付与
応募が完了したユーザーに特典や景品をスムーズに届けましょう。
ギフトやクーポンを発行し、当選連絡メールやメッセージで速やかに通知します。
景品とは別に、応募してくれた方全員に次回来店時に使える割引クーポンなどを渡すと、来店促進へつなげられます。
さらに、効果検証のためのデータ収集と分析も欠かせません。
キャンペーンの終了後は、次のような指標を確認します。
もし改善点があれば、次回のキャンペーン開催時に活かしていきましょう。
- QRコードのスキャン数・応募数
- 応募完了率(スキャンから応募完了までの割合)
- SNSシェア数(シェアキャンペーンの場合)
- クーポン使用率・来店数(集客型の場合)
これらの数値から効果が出た仕掛けを強化し、反応の弱かった部分は改善すると、継続的に成果を上げやすくなります。
QRコードキャンペーンで押さえておきたい3つのポイント

ここでは、QRコードキャンペーンを効果的に運用するために押さえておきたい注意点をまとめます。
QRコードキャンペーンで押さえておきたい3つのポイント
- QRコードを読み取りやすいデザインにする
- セキュリティ・不正防止対策をする
- QRコードをスキャンしてもらうための工夫をする
準備不足のままキャンペーンを開始すると不正応募の発生や集客効果が出ないリスクがあるため、必ず以下のポイントを確認しましょう。
1.QRコードを読み取りやすいデザインにする
表示するQRコードは、サイズやデザイン次第で読み取りやすさが変わります。
QRコードは、次のポイントを守ってデザインしましょう。
読み取りやすいQRコードのポイント
- サイズ:印刷物なら最低1.5cm四方以上の大きさにする
- 余白:QRコードの端から2mm以上(セル換算で4セル分程度)を目安に四方には十分な白地スペースを残す
- 解像度:高解像度で印刷する(低解像度・薄い色はスキャンエラーの原因になる)
- 縦横比:縦横比を崩さず、正方形を保つ
- 色:黒地・白背景の一色運用にする
QRコードは、小さすぎると読み取れず大きすぎると画質が荒れやすいため、適切なバランスが必要です。
なお、読み取り後の遷移先ページは、必ずスマートフォン対応にしましょう。
未対応のままだと表示が崩れたり、操作がしづらかったりするため、ユーザーはストレスを感じてページを離れてしまう傾向があるためです。
2.セキュリティ・不正防止対策をする
QRコードは便利な反面、不正利用や悪用リスクもあります。
安全なキャンペーン運営のため、以下の対策をおこないましょう。
QRコードキャンペーンのセキュリティ対策
- QRコードはHTTPS対応の安全なページにリンクさせる
- 応募情報を取得する際は、プライバシーポリシーの掲載をする
- 同一人物による複数応募対策(アクセス制限や重複制御など)
偽のQRコードに貼り替える犯罪への対策として、店頭設置時は管理しやすい場所を選びます。
QRコードを配置する場所の注意点
- 第三者の手に触れるような場所に放置しない
- 店側がQRコードを常に目の届くところに置いておく
3.QRコードをスキャンしてもらうための工夫をする
せっかくQRコードを設置しても、スキャンされなければ意味がありません。
参加率を上げるためのひと工夫も、忘れずに取り入れましょう。
QRコードをスキャンしてもらうためのポイント
- QRコードの近くに「今すぐ特典ゲット」など短い誘導文を添える
- ユーザーが手に取りやすい位置、目につく場所に配置する
- 複数置く場合は距離も配慮する
高さ、角度、距離が適切か確認するためにも事前に読み取りテストをおこないます。
チェックする際は、複数のスマートフォンで試して、読み取りにくさや不具合がないかを確認しましょう。
参考にしたい!QRコードキャンペーン2つの成功事例

ここからは、実際に成果を上げたQRコードキャンペーンの事例を2つ紹介します。
QRコードキャンペーン3つの成功事例
- 動画からQRコードを見つけて応募するキャンペーン
- QRコード付き抽選券を配布するキャンペーン
自社企画のヒントに、ぜひ役立ててください。
1.動画からQRコードを見つけて応募するキャンペーン

東洋水産が展開したQRコードキャンペーンは、スーパーなど店頭の動画広告と連動している点が特徴です。
スーパーマーケットなどに設置されたデリッシュキッチンのモニター動画を観て、表示されるQRコードを読み取ると応募ができます。
デリッシュキッチンのモニター動画を観ないと応募できない設計にすることで、商品の理解促進と購買行動へのスムーズな動線を実現しています。
QRコードからアンケートに答え、抽選ルーレットを回すと「当たり」「プラチナ当たり」「はずれスペシャル」いずれかの抽選結果がその場で表示されるため、ゲーム感覚で楽しく参加できる点も注目したいポイントです。
2.QRコード付き抽選券を配布するキャンペーン
八重洲地下街では、ポイントを貯めて参加できるQRコードキャンペーンを実施しました。
対象店舗での購入額に応じて、QRコード付きの券を配布し、読み取ることでポイントが加算される仕組みです。
ポイントは3,000ポイントごとに1回抽選に参加できる仕掛けになっており、期間中はポイントを貯め続ければ何度でも抽選に挑戦できます。
繰り返し抽選に挑戦できる仕組みが、来店頻度の向上とリピート促進につながりました。
キャンペーンの景品ならデジタルギフトの「デジコ」

QRコードキャンペーンの成果を高めるには、「参加したくなる景品選び」も重要です。
近年では、受け取り手の選択肢が多く、幅広い世代・性別に喜ばれやすいデジタルギフトの活用が増えています。
「デジコ」は、法人向けのデジタルギフトサービスです。
最大6,000種類の交換先から参加者が好きなギフトを選べるため、年齢層や性別を問わずに喜ばれています。
API連携を活用したギフトの自動発券や、導入後、CSV発注なら2時間以内で発券できる仕組みがあるため、大量のギフト配布でもスピーディーかつ効率的に対応できます。
「具体的にどのようなシーンで使われているのか知りたい」「詳細な料金が気になる」場合は、下記からサービス資料をご覧ください。
まとめ:QRコードキャンペーンで販促効果を最大化しよう
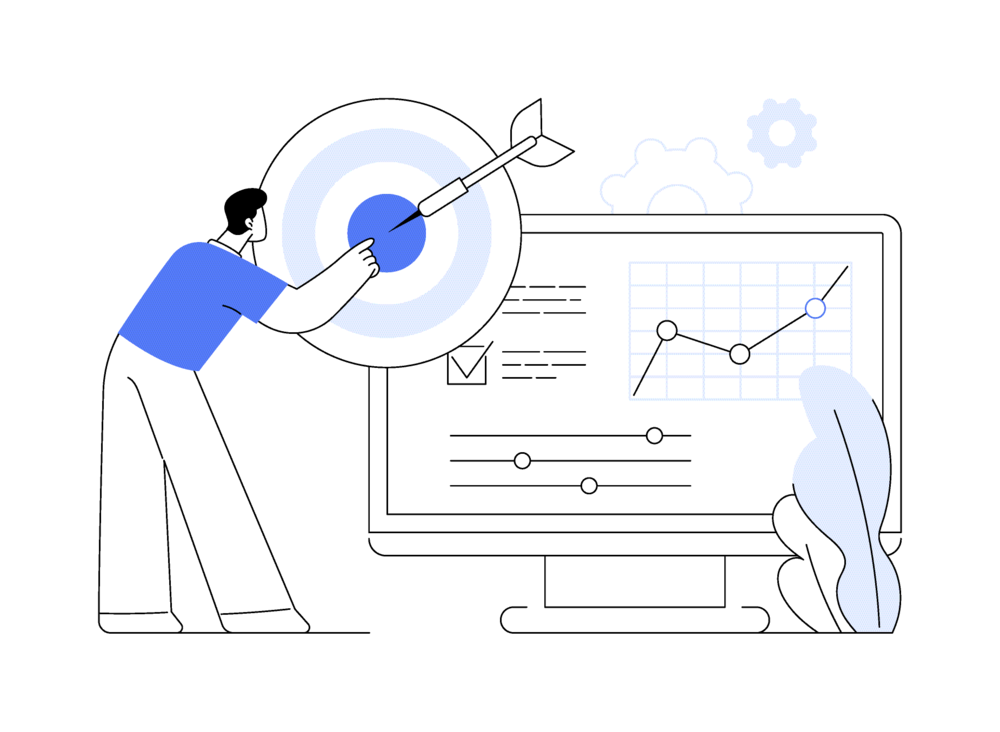
QRコードキャンペーンは、シンプルな仕組みで参加ハードルが低く、幅広いシーンで活用しやすい施策です。
ユーザーはスマートフォンから簡単に参加でき、運営側も効率よく応募情報を集められます。
QRコードキャンペーンの効果を最大化するためには、「目的に合った設計」「読み取りやすいQRコードの工夫」はもちろん、「魅力的な景品設定」が欠かせません。
デジタルギフトのようにターゲットを問わず喜ばれる景品を選ぶことで、参加率も高められます。
本記事で紹介した流れや事例を参考にしながら、効果的なQRコードキャンペーンを実施してみてください。
喜ばれやすいデジタルギフトをキャンペーンの景品にするなら、法人専用のデジタルギフト「デジコ」がおすすめです。
法人専用で大量配布や運用の効率化ができる仕組みがあるデジコは、1,600社を超える企業に選ばれています。
「デジタルギフトをキャンペーンに導入したいけど、やり方がわからない」「キャンペーンの景品選びに迷っている」という方は、下記の資料からデジコの活用方法や詳細をぜひご確認ください。