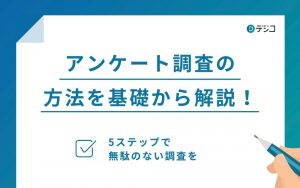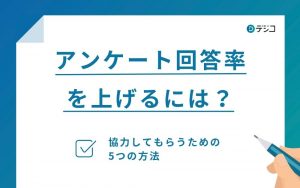デジタルギフトお役立ち記事

アンケート調査の設計のやり方とは?設問作りに役立つ7つのコツを解説
アンケートを実施するにあたり、どのように設問を作るべきか迷うことはありませんか?
設問設計ができていないとアンケートの回答率や精度が下がり、せっかくの調査が無駄に終わってしまいます。
そこでこの記事では、アンケートの調査設計について以下の内容をお伝えします。
- 設問を作る前にやること
- 設問を作るコツ
- アンケートの精度を高めるポイント
アンケートの調査設計や設問の作り方に悩んでいる場合は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
デジコでは、アンケート調査が初めてという方に向けた「初めてのアンケート調査でも失敗しないための全ノウハウ」をご用意しています。
アンケート調査の流れから、設問設計のポイントなどアンケートにまつわるさまざまな疑問にお答えしていますので、ぜひご利用ください。
なお、以下のボタンより無料でダウンロードいただけます。
アンケート調査ノウハウ資料をダウンロードする
目次
アンケート調査の設計は事前準備から!設問を作る前にやること4選

いきなり設問を考え始めるのではなく、事前準備をすることでより中身のあるアンケート調査ができます。
まずは設問を作る前にやるべき設計について見ていきましょう。
1.ゴールの設定をする
はじめに、アンケートの調査結果を使ってどうしたいのかゴールを決めます。
何を知りたくてアンケートを実施するのか、得た回答をどのように使うのかが定まっていないと、アンケートをしても調査結果をうまく活かせません。
例えば以下のようなゴールが考えられます。
調査目的例
<市場ニーズの把握>
- 商品への好感度を調査したい
- 新製品を企画するためのアイディアが欲しい
- ユーザーの反応を見て複数ある商品案を絞り込みたい
<課題の発見>
- 現状の具体的な課題を仮説検証したい
- 顧客満足度を高めたい
- 売上を上げたい
- リピート率を高めたい
など
アンケートを実施するきっかけや成し遂げたい目標をふまえて、「回答者からどのような情報を得たいのか」というゴールを具体的に考えましょう。
2.ゴールに向けた課題を考える
続いて、はじめに決めたアンケートのゴールについて、達成するために必要な課題を明らかにしましょう。
例えば「売上を上げたい」がゴールだとすれば、「売上が上がっていないのはなぜか」を考え仮説を出します。
例
仮説1.商品に見直すべきところがある?→〇〇を直せば改善されるのでは?
仮説2.商品の認知度が低い?→認知度を上げるには〇〇をすれば良いのでは?
この仮説を課題とし、アンケート調査で検証します。このように課題が明らかになることで、アンケートで何を聞くべきかが見えてきます。
3.課題から調査内容を決める
最後は、課題をもとに調査する内容を決めましょう。「課題を解決するために必要な情報」をアンケートで調査することになります。
| 仮説 | 調査内容 |
|---|---|
| 商品に見直すべきところがある? | ユーザーが商品に満足していないポイントをどこか調べる |
| 商品の認知度が低い? | 商品の認知度や、ターゲット層がどこで新商品の情報を得ることが多いのか調べる |
仮説を立てて調査内容を決めることで、あてずっぽうでアンケート設問を考えることがなくなります。
ターゲットの設定・調査手法を選定する
調査の方向性が定まったら、ターゲットとなる回答者を選定します。
ターゲットは、性別・年齢・職業などの属性や顧客・見込み顧客であるかなどから選ぶのが基本です。
ただし、回答者の条件を絞り込みすぎると、アンケートに必要な数を確保できない場合もあるので、比較用としてターゲット以外の属性に聞くことも考慮しましょう。
あわせて、調査費用を算出してアンケート実施のタイミング・募集人数・期間も決定します。
アンケート調査方法の種類については以下の記事でまとめていますので、こちらもぜひご覧ください。
ここまでがアンケート調査設計の事前準備です。続いては設問の作り方について具体的に見ていきましょう。
アンケート調査の作り方は?設問設計の7つのコツ

アンケートの設問は「回答者の答えやすさ」を重視すると、回答率や調査精度が向上します。それぞれのコツについて解説します。
コツ1.アンケートの構成は流れを意識する
まずはアンケートの骨格となる構成を作りましょう。知りたいことをすべて洗い出してから目的に合った質問のみに絞り込むと、取りこぼしがなくなります。
回答しやすいアンケート構成にするには「全体→詳細」の流れを意識することがポイントです。なお、時系列を意識する場合には「過去→現在→未来」の順序が自然です。
回答しやすいアンケートの構成例
属性に関する質問
Q1:性別、年齢、家族構成
↓
選択型の質問
Q2:自社シャンプーを購入したことがあるか
「商品画像」
Q3:自社シャンプーの購入の決め手(複数選択可)
Q4:自社シャンプーに対する満足度(複数選択可)
↓
自由記述型の質問
Q5:Q4の理由を聞く
その他、商品について聞く場合は商品画像を用意するなど、回答者目線に立ち、回答のしやすさを重視して作ります。
コツ2.回答者が負担を感じない設問数に絞る
アンケートの設問数は、回答者が負担に感じない数に絞るのがおすすめです。
設問数が多く時間がかかるアンケートは、負担が大きいため回答者が集まらないことが考えられます。
さらに、時間がかかると回答者の集中力も下がりやすく、設問の後半になるにつれて回答が雑になってしまう恐れもあるでしょう。
回答者が負担を感じにくい設問数としては、多くても20~30問程度(回答時間10分程度)が目安です。
コツ3.思考停止で答えられる設問にする
アンケートは回答に迷うと回答率が下がりやすいため、思考停止で答えられる質問をしましょう。
調査内容にもよりますが、考えずに答えられるよう回答の選択肢を用意しておくのがおすすめです。
ポイントは「意見を聞く」のではなく「事実を尋ねる」ことです。
例
✕:不満な点を教えてください
〇:不満な点を以下よりお選びください
回答者に答えを考えさせず、提示した選択肢の中から事実を選んでもらったほうが気軽にアンケートに答えられます。
コツ4.選択肢の尺度をよく検討する
回答として5段階の選択肢を提示することがありますが、選択肢の尺度は設問にあわせて検討しましょう。
選択肢の尺度の例
- とても好きだ
- やや好きだ
- どちらともいえない
- やや嫌い
- とても嫌い
特に注意したいのは、中立的立場の「どちらともいえない」を選択肢に提示する場合です。
回答者は中立的な意見にできるため考える負担が減る一方で、回答が集中した場合に調査結果を分析しにくいことが考えられます。
「中立的立場の回答が多かった場合でも調査結果を活かせるか」という視点を考えたうえで、選択肢の尺度を決めるのがおすすめです。
コツ5.1つの設問で2つ以上の問いかけをしない
原則として、1つの設問で聞くことは1つにしましょう。1つの設問に2つ以上の問いかけをすると、どちらに対して答えて良いか回答者が迷ってしまいます。
例えば「商品Aの見た目と機能性についての感想を、以下よりお選びください」という設問があるとします。
回答者が、見た目は「とても好きだ」が機能性は「普通」という感想をもっていた場合、うまく回答することができません。
アンケートの調査精度を上げるためにも、設問に対する明確な答えが得られる問いかけにしましょう。
コツ6.さまざまな解釈ができる問いかけをしない
複数の意味・解釈にとれる聞き方をしないことも大切です。回答者が間違った解釈をしてしまうと、本来聞きたかった答えを得ることができません。
例えば「甘いスイーツは好きですか?」という設問があるとします。一見問題ないように見えますが、この設問は以下のように2つの解釈ができます。
- スイーツのなかでも、特に甘いスイーツが好きか聞かれている
- 「スイーツ=甘い」という前提で、スイーツ全般が好きか聞かれている
解釈1では「スイーツは好きだけどそこまで甘いのは好きではない」という回答者がいた場合、答えが変わってしまいます。
また、設問に主語をいれることも忘れずに意識しましょう。主語がないと、「個人について」なのか「家族全員を含めて」なのかがわかりにくくなります。
例えば以下のような場合です。
使用頻度を聞く場合
✕:どのくらいの頻度で〇〇を使用しますか
◯:あなたはどのくらいの頻度で◯◯を使用しますか・家族全員で◯◯を使う頻度を教えてください
誤解が生まれると調査結果にも影響が出るため、設問文はできるだけ具体的に作り、完成したら第三者チェックをしてもらいましょう。
設問文は、回答率にも大きく影響します。回答率をアップさせるアンケートの作り方を知りたい場合は、以下の記事もご一度ください。
コツ7.得たい内容によって適切な回答形式を選ぶ
アンケートには、さまざまな回答形式があります。「どのような回答を得たいのか」を想像したうえで、質問項目に応じた回答形式を選ぶようにしましょう。
主な回答形式
<単一選択型>
回答を選択肢のなかから1つだけ選択する
例:「はい/いいえ」「購入したことがある/ない」など経験の有無、購入歴など事実を聞く
<複数回答型>
3つ以上の選択肢のなかから当てはまるものをすべて選択する(選択数を指定する場合もある)
例:商品のイメージを聞く・購入動機・金額や年数を区切る場合などがある
<段階評価型>
5段階や7段階などの尺度からもっとも当てはまる尺度を選択する
例:顧客満足度を聞く、ブランドイメージを聞く
<順位型>
選択肢のなかから順位をつけて当てはまるものを選択する
例:購入したい優先順位を聞く
<自由記述型>
自由に文章などで回答できる
集計が難しいためあらかじめどのような形で集計するか考えておく必要がある
例:購入理由を詳しく聞く、商品に関する意見や要望を聞く
回答形式の選定は「集計しやすさ」「回答しやすさ」の両方に関わってきます。上記を参考に、質問内容に適した形式を選びましょう。
なお、デジコではアンケート調査が初めてという方に向けた「アンケートノウハウ資料」を無料配布しています。
以下のボタンより無料でダウンロードいただけますのでご利用ください。
資料をダウンロードする
ここまでが設問の作り方のコツでした。ただ、アンケートの実施にあたり、より調査精度を高めるポイントがあります。続けて見ていきましょう。
アンケート調査の精度を高めるために確認したい6つのチェックポイント

ここでご紹介するのは、設問を作り終えたあとに意外と忘れがちなポイントです。これらのポイントに気を付けると、調査精度をさらに高めることにつながります。
ポイント1.回答者の属性に関する項目はあるか
どのような人がアンケートに答えたのか知るために、回答者の属性について尋ねる項目を入れましょう。
属性ごとの調査結果を分析しやすくなり、今後の商品開発やプロモーション施策につなげられます。
属性の項目例
- 年齢
- 性別
- 居住エリア
- 職業
など
ポイント2.設問が適切な順序で配置されているか
作成した設問は、答えるのが簡単な設問を最初のほうに持ってくるのがおすすめです。
最初から複雑で難しい問いかけをされると、回答者が「面倒くさそう」と感じてしまいます。
アンケートは任意で協力してもらうことが多く、回答者は少しでも早く終わらせたいと思うものです。
面倒に感じた時点で、適当に答えたり途中で回答をやめてしまったりするかもしれません。
調査精度の低下を防ぐためにも、簡単な順から設問を並べて回答者の負担を減らしましょう。
ポイント3.設問にモレ・ダブりがないか
アンケート実施前に、作成した設問にモレ・ダブりがないかチェックしましょう。
設問内容にモレ・ダブりがあると、調査しきれない部分が出てきてアンケートの精度が落ちます。
「モレなく、ダブりなく」というのを、マーケティング用語ではMECE(ミーシー)といいます。MECEになっていないNGの設問例を見てみましょう。
春休みの旅行先はどこですか?
- 国内
- アメリカ
- ヨーロッパ
- ハワイ
上記の例は、他の地域へ行く人の選択肢がないモレがあり、ハワイはアメリカなのでダブりがあります。
設問の作成者がモレ・ダブりに気付かない場合もあるため、他の人にもチェックしてもらうと良いでしょう。
ポイント4.アンケート内容はシンプルか
アンケート内容は、できる限り回答者に負担をかけず、誰もが回答できるようなシンプルな内容を心がけましょう。
パッと見て「時間がかかりそう」「ややこしい」などと思われてしまうと離脱されてしまう可能性が高まります。
具体的には以下のような場合です。
悪い例
- 冒頭の挨拶が長文
- 質問が長すぎる、過度な敬語を使う
- 専門用語や業界用語を使う
- 曖昧な表現を使っている
- 選択肢が多すぎる
- 回答が自由回答形式のみ
より回答率を上げるためにも、複雑な内容になっていないかを事前確認しておくことが重要です。
ポイント5.個人情報の取り扱いについて伝えられているか
アンケートで氏名や住所、メールアドレス、会員番号などの個人を特定できる情報を集める場合は、個人情報保護法に則って適切に管理する必要があります。
具体的には以下の3つの事項を守らなければなりません。
- 個人情報の使用目的を明示
- 個人情報を第三者に提供しない旨を記載
- 個人情報の問い合わせの窓口を設置
また、設問内容に以下のようなプライベートな回答を求める場合にも、事前に承諾をとり、「個人が特定されることはない」と記載しておきましょう。
- 学校名や会社名
- 年収
- 病歴・疾患
事前の説明があるとアンケートの信頼性が上がり、離脱率も下がります。
ポイント6.事前に回答テストは行っているか
アンケートが完成したら、実際にアンケート回答のテストをおこなうことをおすすめします。テストでは、かかる時間、調査目的に沿った回答が得られるかをチェックしましょう。
特に回答にかかる時間の確認は、回答率を上げるためにも重要です。
時間のとられるアンケートは相手の負担となります。最低でも10分以内で終わるような長さに設定しましょう。
もし、どうしても時間がかかってしまう場合やプライベートに関わる内容の場合には、謝礼を高くするなどの配慮を検討します。
アンケートの回答率アップのために謝礼を用意するのも効果的

アンケートは任意で回答してもらうため、回答者に何らかのメリットがあると協力してもらいやすくなります。そこで効果的なのが、謝礼品を用意することです。
「どのような謝礼品が良いだろう」と迷うと思いますが、モノやサービスなど直接的な利益になるお礼が喜ばれるでしょう。
謝礼品としておすすめなのはデジタルギフト(オンラインで贈れるギフト)です。
デジタルギフトなら、電子ギフト券・各種ポイントなどを、SNSやメールを通してプレゼントできます。
デジタルギフトがアンケート謝礼におすすめの点
- 郵送する手間や費用がかからない
- データで管理できるため在庫置き場がいらない
- 必要数だけすぐ発注できるため在庫が余らない
- 幅広いギフトがあるため人を選ばず贈りやすい
デジタルギフトのなかには、アンケートの集計作業をまとめて任せられるサービスもあります。
デジタルギフトの「デジコ」の場合は、即日納品(発注から2時間以内に発券)できるため、急ぎのアンケートにも対応可能です。
アンケート調査にデジタルギフトを活用するメリットや導入事例については、以下の資料でまとめています。
どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。
資料をダウンロードする
まとめ:アンケート調査は入念な設計が大切
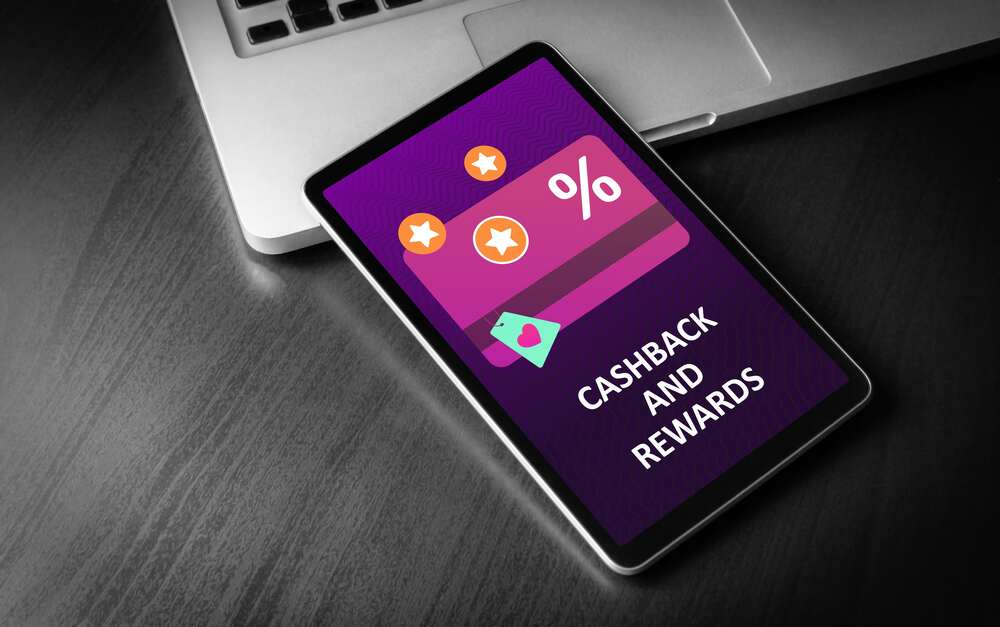
この記事では設問の作り方や調査精度を上げるポイントなど、アンケート設計についてお伝えしました。
設問はいきなり作り始めず、まずはゴール設定や調査内容を決めることで中身のあるアンケートができます。
設問を作る際も「回答者の負担は少ないか」という視点で考え、回答率や精度アップにつなげましょう。
入念に設計し、アンケートをマーケティングや施策に活かしましょう。
なお、デジコでは、アンケート調査が初めてという方に向けた「初めてのアンケート調査でも失敗しないための全ノウハウ」をご用意しています。
アンケート調査の流れから、設問設計のポイントなどアンケートにまつわるさまざまな疑問にお答えしています。
資料は以下のボタンより無料でダウンロードいただけますので、ぜひご利用ください。アンケート調査ノウハウ資料をダウンロードする